週報
説 教 題 「多くの人を富ませる貧しさ」
聖書個所 コリントの信徒への手紙Ⅱ6章3節から10節まで
讃 美 歌 332(54年版)
アイデンティティーという言葉があります。「自己同一性」と日本語で訳される言葉ですが、簡単に言えば、「自分はいったい何者であるか?」という問いに対する自己意識を表す言葉です。自分はどういう人間なのか?どういう存在なのか?という自己の存在を問う問いは、自分は何のために生きているのか?という問いに直結するような深刻な問いであると言うことができると思います。
しかし、普通、私たちの一般的な感覚では、アイデンティティーというものが問題となるのは、若者にとってだろうと思っています。たいへん青臭い印象のある「自分探し」という言葉と相俟って、自分が一体何者であるかというアイデンティティーの問いに翻弄されているのは、たいてい若者だろうというのが、私たちの一般的な考えであるかもしれません。
けれども、最近になってむしろ、よく知られるようになってきたことは、アイデンティティ―の問いというのは、麻疹のように若い内に一度かかり、それを乗り越えればそれでおしまいというわけにはなかなかいかないということです。たとえば、最近切れやすい中高年、特に高齢者が増えているということが言われることがありますが、聖路加病院の精神科医の方の解説によると、退職前の肩書に執着する人ほど、短気になる傾向があるということだそうです。会社で受けてきた尊敬が家庭や街中では得られない、自分が今までの自分のように扱われないということで、感情が爆発してしまうというのが一つの原因であるそうです。先生と呼ばれるような仕事をしている私なども、将来、典型的にそういう切れやすい人間になるのではないかと、妻などはかなり心配していますし、引退後に出席する教会で、そこの現役牧師を困らせることは自分でも十分ありうるなと思っています。
しかし、それは、定年退職後に限らず、結婚前後や、休職して何年も子育てをする期間、また、子どもの独立後、愛する者と死別した時、あるいは自分が大きな病を得た時、大きな失敗をしでかした時、住み慣れた家を離れたり、それまでの自分とは違った生活を始めなければならない時には、いつでも、アイデンティティーの危機が訪れ、自分が誰であるかわからなくなり、自分が何のために生きているのかすらわからなくなってしまうようなことというのは、若者に限らず、何歳であっても、起こり得ることだと思います。
そういう時に、どんな危機が訪れても、決してぶれない自分を持っているということは、とても心強いことであり、ぜひ、そうありたいものだと願うことは、私たちの人情というものだと思います。
今日ともに読んでいます聖書の言葉は、まさにそのような私たちにとって、興味のある個所であります。
4節において、パウロはあらゆる場合に自分が示し続けることのできる「実」(じつ)があるのだと言います。あらゆる場合において、自分は自分の実(じつ)を示し続ける。実(じつ)という翻訳は、新共同訳聖書の味わい深い翻訳だと思います。元のギリシア語では、「自分自身を示す」という言葉が使われています。コリント書全体においては、パウロの使徒としての正当性が問題となっているわけですから、「自己証明」「自己推薦」と訳した方が、意味は通りそうですが、私は「実」という翻訳も、許されるのではないかと思います。パウロの誠実とか、真実とか、あるいは、パウロの実存と言ったって間違いではないと思います。
あらゆる場面でパウロをパウロ足らしめている実存、どんな困難な状況の中に陥っても、我を見失わず、「これが私です」ということのできるパウロの実存、アイデンティティー。堅固なアイデンティティー、したたかでしぶとい実存です。それは、4節の言葉で言えば、「神に仕える者」であるパウロの実存です。
この実存がどれほど頑丈なものであるか?パウロは、「苦難、欠乏、行き詰り、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても」、打ち破られることなく、その「実」を示し続けていると言います。さらに、8節では、「栄誉を受けるときも、辱めを受けるときも、悪評を浴びるときも、好評を博するときにも」と言います。彼はいついかなる時にも、自分が「神に仕える者」であることを見失うことはありません。そのアイデンティティーが、取り去られることはないし、だから、自分の生きる目的を見失うこともありません。
私たちは、ここで挙げられるものの内、苦難、欠乏、行き詰まりくらいは知っていると思います。しかも、ただのその一つだけでさえ、大きく揺さぶられてしまいます。けれども、パウロは、鞭打ち、監禁、暴動と、私たちの内のほとんどの者は、おそらく一生の内に一度も経験することのないような状況に置かれても、彼は、「神に仕える者」である自分の「実」を、見失うことはなかったと言います。驚くべきことです。
蛇足のようですが、パウロが挙げた様々な危機的状況の内で、8節の「栄誉を受けるとき」、「好評を博するとき」という状況が取り上げられていることは、意外なようにも思いますが、よく考えてみれば、これも自分を見失うことになりがちな大きな危機なのだと納得させられます。褒められて得意になって、自分を見失って、「豚もおだてりゃ木に登る」という新しい諺がありますが、登って登って、もう登るところがなくなって木から転げ落ちたら、周りにはもう誰もいないということは、あることだと思います。伝道者であるパウロにとっては、栄誉を受けるとき、好評を博するときというのは、伝道がうまくいき、洗礼を受ける人が続々と与えられるというような時だったでしょうから、それこそ、自分は神さまに用いられている、神の特別な器だと鼻高々になれたでしょう。けれども、パウロは、そんなときも自分は「神に仕える者」であるという自分を見失わないのだと言います。
この「神に仕える者」という言葉、口語訳聖書では「神の僕」と訳されていました。僕というのは、奴隷のことです。少し前に、「神の協力者」ということが書いてありましたから、それは誤解が生じやすい。あたかも、人間が神様の助け手となって、神さまの足りないところを補っていくような、まるで神さまと対等な関係であるかのような誤解を避けるために、神に仕える者、神の僕と、ここで言い直さなければならなかったのでしょう。奴隷は主人の所有物ですから、奴隷のすることは主人のすることの延長です。だから、主イエスもまた、その弟子たちにあなたがたはすべきことをしたら、「わたしどもは取るに足りない僕です。しなければならないことをしただけです」(ルカ17:10)と言いなさいと教えられました。パウロは、そういう神の僕である自分を見失わないのです。栄誉を受けても、好評を博しても、「私は神の使者だから、褒められて当然」と鼻高々にはなりません。取るに足りない僕である自分を見失わないのです。
しかし、このような神の奴隷であるからこそ、逆に、辱めを受けるときも、悪評を浴びるときも、自分を見失うことがありません。なぜならば、主人の所有物である僕に与えられた侮辱と汚名は、主人自身に浴びせられた侮辱と汚名であり、その名誉を回復することは、主人自身の仕事であるからです。
聖書の中には、これはパウロ自身について言えることですが、二つの異なったように見えるキリスト者のアイデンティティーを語る言葉があります。一つは神の僕、神の奴隷という言葉であり、もう一つは、神の子、キリストと共同の相続人であるという言葉です。これはどちらがより根源的なものかというものではなく、両方正しいのです。両方が補い合って、決して崩されないどんな危機にも耐える人間のアイデンティティーを形作ります。
すなわち、私たちは奴隷である限り、自分で自分のものを持ちません。自分が誰であるかなんて、何も持たない僕であるとしか、答えようがありません。その意味で、私たちは自分のアイデンティティーなど自分で守ることなどできません。人間のアイデンティティーなんてものは、青年期に確立すれば一生安泰なんてものではない。ずーっと翻弄され続ける。ずーっと揺らぎ続ける。キリスト者たちは世の人たちと同じように、それがどんどん打ち崩されることを、加齢や、経済の浮き沈み、世の動乱と共に、一緒に体験しなければなりませんし、むしろ、ある面では、世の人の誰よりも深く、揺らぎを経験するものだと思います。なぜならば、キリスト者は、たとえ、一生涯社会的には、人の好評を博するような地位に留まれたとしても、それが神のみ前で自分が誰で何者であるかを語る自分の実存にはなりえないことを誰よりも厳しく知らなければなりません。私たちは神の前に常に無一物の奴隷であることを知らねばなりません。何も持てるものがない者として、ただ日毎に主人である神が与えてくださる天来のマナと呼ばれたパンによって、一日一日と養われなければなりません。
しかし、神は養ってくださるのです。神が恵みを取り去れば、一瞬たりとも立つことのできない私たちを、神は日毎に養うことを、永遠に決意してくださっているのです。この何も持たない僕を、今日一日、神の子として生かす。今日も、明日も、明後日も、神は永遠にこの無一物の者を、ご自身の子として、キリストと共同の相続人として扱ってくださるのです。
コロサイの信徒への手紙もまた、パウロと同じように、私たちの命は私たちの命は私たちの手の内にではなく、「キリストと共に神の内に隠されています」(コロサイ3:3)と言います。自分で自分のアイデンティティーを、実存を、この手でしっかりと握りしめることができない、私は何も持たない僕であるということは、とても心許ないように思えますが、握っているのは、私ではなく、神様ですから、本当はその方が心強いのです。だからこそ、信仰者は、時に人の想像を超えて、しぶとく、強く、勇気に満ちているのだと思います。普通の人がへこたれても、参らないのです。希望を失わないのです。
以前も紹介したことがあったと思いますが、今から70年以上前、ドイツで、反ナチスの運動を展開し、逮捕され、処刑されたD.ボンヘッファーという人が、獄中で書いた詩に、「私は何者か」という題の詩があります。まさに、信仰者のアイデンティティーのぎりぎりのラインを物語る詩であると思います。
少し長いですが、全文引用します。
私は一体何者か。
悠然として、晴れやかに、しっかりした足どりで、
領主が自分のやかたから出て来るように
獄房から私が出て来ると人は言うのだが。
私は一体何者か。
自由に、親しげに、はっきりと、命令をしているのが私の方であるように、
看守たちと私が話をしていると人は言うのだが
私は一体何者か。
平然とほほえみを浮かべて、誇らしげに、
勝利にいつも慣れているように、不幸の日々を私が耐えていると
人は言うのだが。
私は本当に人が言うような者であろうか。
それとも、ただ私自身が知っている者にすぎないのか。
籠の中の鳥のように、落ち着きを失い、憧れて病み、
のどを締められた時のように、息をしようと身をもがき、
色彩や花や鳥の声に飢え、やさしい言葉、人間的な親しさに恋いこがれ、
恣意や些細な侮辱にも怒りに身を震わせ、
大事件への期待に追い回され、
はるかかなたの友を思いわずらっては気落ちし、
祈り、考え、活動することに茫然とし、意気阻喪しつつ、
あらゆるものに別れを告げる用意をする。
私は一体何者なのか。
前者であろうか、後者であろうか。
今日はある人間で、明日はまた別の人間であろうか。
どちらも同時に私なのであろうか。
人の前では偽善者で、
自分自身の前では軽蔑せずにはおられない泣き言を言う弱虫であろうか。
あるいは、なお私の中にあるものは、
既に勝敗の決した戦いから、算を乱して退却する敗残の軍隊と同じなのか。
私は一体何者なのか。
この孤独な問いが私をあざ笑う。
私は何者であるにせよ、
ああ神よ、あなたは私を知り給う。
私はあなたのものである。
キリスト者というのは、キリストの者であるということです。キリストに所有されたキリストの僕、キリストの奴隷だということです。僕は自分が誰で何者であるかなんて究極知らなくっていいんです。おかしな言葉に聞こえるかもしれませんが、自分のアイデンティティーなんて一生懸命訪ね求めなくたって良いというのが、僕のアイデンティティーです。
栄誉を受けても、辱めを受けても、悪評を浴びても、好評を博しても、人を欺いているようでいても、人に知られていないようでいても、死にかかっているようでいて、罰せられているようでいても、物乞いのようでいても、無一物のようでいても、それらの只中にあって、自分を見失ってしまっても、一向に構いません。
私がわからなくなる時も、神は私たちを知ってくださいます。私たちは神の所有です。アイデンティティーが私たちを生かすのではなくて、死にかかっている私に、「生きよ」、「生きてよい」と呼びかけてくださる神の言葉が、生かすのです。
大切なことは、私たちが自分を神のこと知ることではなくて、神さまが私たちをご自分のものと知り続けてくださること、呼び続けてくださるです。
以前仕えていた教会で、お歳を召し、施設に入り、お尋ねしても、もううまく会話が嚙み合わないという方がおられました。聖餐訪問にお尋ねするのですが、鎌倉らしいこととは思いますが、「私は大仏の子、大仏の娘だ」って言うんです。なんて反応すればいいか戸惑うのですが、粛々と礼拝を行い、説教を語ります。すると、途中でハッとした顔付きに変わるんです。それで仰います。「忘れていました。私は神さまの娘でした。」
また別の施設で暮らす同じような状態の別の方も、この方は、あるとき説教中に立ち上がって仰いました。「福が来た。福が来ましたよ。」って。
私たちが忘れてしまっても、神さまはお忘れにならないんです。思い出させてくださいます。いや、思い出せなくたって、事実は変わりません。神は、ご自分の僕を、お見捨てになることはありません。そもそもそれがイエス・キリストがこの地上に送られてきた理由でした。
そう考えますと、この約束、この恵みは、まず初めに私たちが聞かせて頂きましたが、私たちに留まるものではありません。神が愛されたのは世です。神が取り戻そうとされたのは、神さまのことをすっかり忘れてしまっている世です。
それゆえ、神は、その神の僕である私たちを、6節に記された純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉という神の善き力に日毎に囲み、私たちをお遣わしになります。
この世を取り戻すために、その独り子をさえ惜しまずに、私たちに与えてくださった方は、ご自分の福音を告げ、私たち教会に必要な備えを必ずお与えになります。そして必ず、世を福音によって生かされます。私たちもまた、自分のことはすっかりお任せして、ひたすら神の喜ばれる歩みを作らせてくださいと祈りたいと思います。
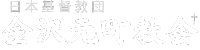
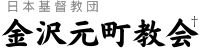
コメント