週 報
聖 書 ヨハネによる福音書12章36b~43
説教題 主が主であるということ
讃美歌 18、392、29
教会の中で教わり、困難にぶつかるとき、度々思い出す言葉があります。
それは、「最後から一歩手前の真剣さで」という言葉です。
私たちが、もう駄目だ、これで終わりだと思うことに直面したとしても、それは最後から一歩手前なんだ。終わりだと思っているところは終わりではなく、その先に、本当の結末が待っている。
どんなに真剣に悲しまなければならない状況の中に身を置いていたとしても、どんなに深刻に悩まなければならない状況に投げ込まれているように感じているとしても、その真剣さ、深刻さは、決定的なものではない。
もちろん、リアルな悲しみ、現実の苦しみであることは間違いないし、悲しいのも、苦しいのも、居たたまれないのも、つらくて仕方のないのも幻想ではありません。
それは見ないことにはできません。笑い飛ばすこともできないかもしれません。
けれども、そうはあっても、それは、最後から二番目のもの、終わりの一歩手前の状況、終わりではないと信じて良いのです。
そのことをいつも覚えておくように、絶望し切らないで良いと招く言葉です。
それでは、最後の最後のものとは何か?
神の支配です。この世界と歴史は、悪魔が支配するものではなく、神が支配するもの、この世界と歴史は私たち人間の罪が支配するものではなく、主なる神が、真の主人として治めてくださるもの、それが最後のものです。
内村鑑三という明治時代のクリスチャンは、これを忘れがたい言葉で言いました。
「この世の中はけっして悪魔が支配する世の中にあらずして、神が支配する世の中であるということを信」ぜよ、「失望の世の中にあらずして、希望の世の中であることを信」ぜよ、「この世の中は悲嘆の世の中でなくして、歓喜の世の中であるという」ことを信ぜよ。
だから、どんな試みにあう時も、それは最後ではない。最後から一歩手前の真剣さで生きて良い、これがキリスト教会の信仰です。
今、夜の祈祷会では、旧約のホセア書を読み進めています。
10人以上の参加者と共に、ああでもない、こうでもないと、楽しい聖書黙想の分かち合いをしています。一回につき一章、礼拝説教で読むのと比べれば、ずいぶん長めに読んでいます。
何回か、読み進めて、第4章に入ってから、今、少し読むのが苦しいような箇所が続いています。何で読むのが苦しいかと言えば、裁きの言葉が続いているからです。丸々一章読んでも、最初から最後まで、神さまの裁きの言葉しか書いていない。それどころか、5章、6章、7章、8章と11章と連続する文章で、神の民に対する裁きの言葉がこれでもかこれでもかと続きます。
もしも、私たちがヨハネによる福音書を読み進めるペースで、このホセア書を礼拝の中で聴くとするならば、毎週、毎週、何か月にも渡って、ひたすら神さまの裁きの言葉を聴かなければならなくなります。しかし、ずっと同じ苦しい裁きの言葉だからと読み飛ばすことはできません。
こんな厳しい言葉は聴きたくない、教会で聴くような言葉ではないと耳をふさぐこともできません。
聖書の言葉です。神が預言者ホセアを用いて、神の民にお語りになった言葉です。
一体どういう風に読んだら良いか?どんな風に聴いたら良いか?どんな意図をもって、このような言葉を神は預言者に語らせられるのか?耳に痛い言葉を聴かせ続けて、何とかして、その民をご自身のもとに引き戻そうとされているのか?飴と鞭の、鞭のような意図を持つ言葉かと言えば、そうでもありません。
ホセアの預言を真っ直ぐ読むならば、神の民は、戻れないのです。戻ろうとしても、的外れな戻り方しかできない。その悔い改めは、「わたしはお前をどうしたらよいのか。」と神さまを途方に暮れさせてしまうような的外れな戻り方なのです。
つまり、厳しい裁きの言葉も、鞭の役割を果たすことができない。脅されても、なだめられても、どうあっても帰って来ない、的外れな帰り方しかできない神の民の姿が語られているのです。
だから、読んでいて余計に苦しい。救いがないように思えてきます。
ホセア書11:7で、そのような神の民に対する神ご自身の言葉が語られています。
「わが民はかたくなにわたしに背いている。
たとえ彼らが天に向かって叫んでも
助け起こされることは決してない。」
彼らの叫びはもう聞かれない。叫んでも無駄。本心からの叫びではないからです。悔い改めた者の叫びではないからです。
神を神とする者の叫びではないからです。だから、彼らの叫びは、神を動かすことはありません。もう打ち手はありません。
ところが、人間のどん詰まりを思い知らされる厳しい厳しい裁きの言葉であるけれど、それが最後ではないのです。
確かに人間は手詰まりです。しかも、神の民と言われる神に最も近いはずのその人間が、手詰まりなのです。けれども、人間の側からは詰んでしまっている局面において、もはや、その叫びに心を動かされることはないと11:7で言い切った神が、なぜだか、直後の11:8で、このように仰るのです。
「ああ、エフライムよ
お前を見捨てることができようか。
イスラエルよ
お前を引き渡すことができようか。
…わたしは激しく心動かされ
憐みに胸を焼かれる。」
この神の言葉が語られた時、実は、イスラエルは絶頂期にいました。得意になって我が世の春を謳歌していました。このところまで語られた神の裁きの言葉通り、イスラエルは裁かれ、捕囚という苦難の中に入れられ、そのようにして自分の罪の報いを刈り取らなければならなくなりました。
しかし、その裁きの後に、ふさわしくない者であるにもかかわらず、この神の憐みのゆえだけに、滅ぼし尽くされることなく、主に本当に立ち返ることを与えられるのです。
どうあっても、正しい悔い改めに至りえないこの神の民のために、神ご自身が、悔い改めの言葉すら用意してお与えになるのです。
神の憐みと、その憐みが引き起こさずにはおれない人間の悔い改め、真の立ち帰り、それが最後のものなのです。
なぜ、このような憐みを神がお与えになるかと言えば、ホセア書は、「わたしは神であり、人間ではない」から、主が主であるからと、語られています。
今日の聖書箇所であるヨハネによる福音書を離れて、長々と旧約のお話をしました。
しかし、ここに鮮やかになる神の同じ思い、旧新約聖書を貫いて変わることのない神の思いがあると信じ、お話いたしました。
ヨハネによる福音書もまた、今日の箇所だけを読むならば、わたしたちには本当に立つ瀬のない厳しい言葉、裁きの言葉が語られています。
「イエスはこれらのことを話してから、立ち去って彼らから身を隠された。このように多くのしるしを彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。」
この36節後半から、37節の福音書記者の言葉は、直前の出来事のみならず、ヨハネによる福音書ここまで全部のまとめの言葉だと言われています。
主イエス・キリストは多くのしるしを人々の前で行ったけれども、彼らは信じなかった。そして、とうとう、主イエスは彼らの元から立ち去って身を隠された。
直前の35節で、「光は、今しばらく、あなたがたの間にある。暗闇に追いつかれないように、光のある内に歩きなさい。…光のある内に、光を信じなさい」と、言われていましたが、彼らは信じず、光なるお方は立ち去り身を隠されたのです。
これが、ヨハネによる福音書のここまでの記述のまとめだと言うのです。
どんなにしるしを見ても、主イエスの輝きの中にあっても、光を信じることのできない人間なんだ。しかも、神の民と呼ばれる者たちさえ、信じることができなかったのだ。これが、ここまでのまとめ。
主イエスは身を隠され、もはや、泣いても叫んでも、光の内には歩めないところまで来てしまった。
しかし、福音書記者ヨハネは、そうなることはわかっていたのだと言います。
もう既に、預言者たちの時代に、福音書記者は、ホセアではなく、イザヤを引用し、もう、何百年も前の預言者イザヤの時代に、神はこうなることをお語りになっていたと引用するのです。
「主よ、だれがわたしたちの知らせを信じましたか。主の御腕は、だれに示されましたか。」
この言葉は反語、言いたいことと反対の内容を疑問の形で述べているものであり、その答えは、「だれも信じない」です。
神が使者をお遣わしになって、その御心をお知らせになっても「だれも信じない」のです。
福音書記者ヨハネは、このようなひどい不信仰が地を覆っている状況を凝視しつつ、更に言葉を重ねて、イザヤがその理由まで語っていたと、次のように言います。
「神は彼らの目を見えなくし、/その心をかたくなにされた。/こうして、彼らは目で見ることなく、心で悟らず、立ち帰らない。/わたしは彼らを癒さない。」
衝撃的な言葉です。
なぜ、誰も主イエスを信じなかったのか?
神が彼らの目を見えなくし、彼らの心をかたくなにされたから。神が彼らが悟ったり、悔い改めたりできないようにされたから、彼らを癒さないと決心されたから。
恐ろしい言葉です。
しかし、このような言葉によって、福音書記者ヨハネが、人間は神の意思通りにしか動けないロボットのようなものだという運命論を語っているわけではないということにも、注意深く聖書を読むと気付かされます。
神が彼らの目を見えなくし、心をかたくなにされたから悟れない、悔い改められないという言葉に続いて、42節で、それとは矛盾するような言葉がほとんど間髪入れずに記されているからです。
「とはいえ、議員の中にもイエスを信じる者は多かった。」
神が心をかたくなになれたので、誰も信じなかったと言いながら、「とはいえ、議員の中にもイエスを信じる者は多かった。」
字面的にはすごく矛盾しています。
しかし、「とはいえ、議員の中にもイエスを信じる者は多かった。」という言葉に続けて「ただ、会堂から追放されることを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって公に言い表さなかった。彼らは、神からの誉れよりも、人間からの誉れの方を好んだからである。」と語ります。
この続く言葉によって、「神が人の目を見えなくする、心をかたくなにする」という言葉が、何を意味するのか、誤解できないようになっています。
つまり、それは神の介入なしに、私たち人間自身に自由に選ばせるならば、人間自身の判断に任せるならば、私たち人間はいつでも神の誉れよりも、人の誉れを自由に選ぶということです。
神がどんなにしるしを見せてくださろうと、生ける証拠を突きつけようと、こちらが光で、あちらが闇だと、声を大にして叫ぼうと、そしてそれに説得されて、多くの者が心で信じ始めようと、人を恐れ、人をはばかり、神よりも人間を主人とするゆえに、不信仰を必ず選ぶのです。
神ご自身が、人間の自由にお任せになるのなら、人間は滅び以外に選ばないと福音書記者は語っているのです。そのことが、ここまでのところで、明らかにされているのだと、まとめているのです。
先週の朝の祈祷会で、読んだロマ書第7章には、まさにこのような人間の状況を、自分事の実感として呻くように語るパウロの告白の言葉がありました。
「わたしは自分がしていることがわかりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。…わたしは、自分の内には、つまりわたしの肉には、善が住んでいないことを知っています。善をなそうとする意志はありますが、それを実行できないからです。…わたしはなんと惨めな人間なのでしょう。」
旧新約聖書を貫いて、聖書は私たち人間がどういう者であるかを、まとめると、要するにこういう者だと語ります。
神を神と知りながら、神と一緒に歩けない。主を主とすることができない惨めな人間だ。弱い人間だ。貧しい人間だ。
けれども、これが最後の言葉ではないのです。
私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝すべきことに、最後の言葉は、私たちの不信仰ではなく、キリストの真実なのです。
その独り子を賜るほどに世を愛された神は、光よりも闇を好む私たち人間を、御子イエス・キリストにおいて、ヨハネ12:32、「わたしは地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。」と、決めておられました。
神を神とすることができない人間、主を主とすることができないすべての人間を、十字架に上げられるとき、自分のもとへ引き寄せよう。
「ああ、エフライムよ/お前を見捨てることができようか。イスラエルよ/お前を引き渡すことができようか。…わたしは激しく心動かされ/憐みに胸を焼かれる。」
イエス・キリストの十字架の出来事とは神のこの憐みが燃え上がり、形となった出来事です。
主イエスが立ち去ったのは、彼らを見捨てるためではなく、彼らの力によらず、彼らの立ち返りによらず、ただ、ご自身の憐みの十字架により、ご自分のもとに、ふさわしくない者たちを引き寄せるためです。
実に、今日の聖書箇所で引用される裁きの言葉を語るように召された預言者イザヤもまた、人間の分際であり、人間の分際である限り、神の御前に立つことのできない不信仰な人間でありました。
お前たちの目は見えなくされ、心はかたくなにされるという裁きの言葉を語るようにと、生ける神の御前に召し出された時、イザヤは、他の誰でもなくこの自分こそが、神の言葉を悟ることをせず、聴くこともできない、汚れた者、滅ぶべき者であることを知りました。
しかし、イザヤ書6:6によれば、神がお命じになると、天使によって運ばれた熱い炭火が自分の唇に触れる幻をイザヤは見ました。
すると、その天使は言いました。「見よ、これがあなたの唇に触れたので/あなたの咎は取り去られ、罪は赦された。」
これによって、イザヤは、神の御前に立つことが許されました。イザヤを赦し、清める神の憐みの炭火です。
その燃える祭壇の炭火を、はるかに超える神の憐みの燃え上がりの極みである御子の十字架です。
その十字架は一人の人に触れるだけのものではありません。独り子を賜るほどに愛す世のために、この世の只中に、すべての人のために立ったのです。
見よ、世の罪を取り除く神の小羊と、この福音書の冒頭で語られた燃える神の憐みです。その神の炎が、世に触れたのです。
その神の燃える憐みが、世の不信仰を最後にはとかし、燃えカスとするのです。
キリスト者である著名な現代詩人、石原吉郎は、「最後の敵」という詩の中の一節で、神に敵対する私たち人間の不信仰を打ち破るキリストの幻を描いています。
彼はやって来るだろう
かんぬきよりもかたくなな
ぼくらの腕ぐみを
苦もなくおしひらいて
その奇体なあつい火を
ぼくらの胸に
おしつけるために
不思議な不思議な熱い火が、燃え上がる神の憐みが、私たち人間の頑なな腕組みを、私たちの不信仰を苦もなくおしひらいてしまいます。
2000年前の十字架で既にそれは起きました。これから起きることではなく、もう既に、十字架はこの世に触れたのです。
その出来事が語られるところではどこでも、生ける神の霊が働き、熱い火がこの胸に押し当てられます。私たちの頑なな腕組みが解かれまる。
私たちの不信仰を突き破って、神を神とすることが、今、ここで、何度でも私たちの現実となります。神の支配が、神の国が、今、ここで、私たち自身の現実となるのです。
そのために、神の独り子は、十字架を目指して歩まれます。十字架で、神は、人の神となられました。だから、人は必ず神の人となるのです。
だから、皆さんの心にこびりついている不信仰、生ける神の御支配に対する疑いは、深刻なものでもなければ、最後のものでもないのです。
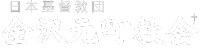
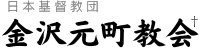
コメント