週 報
聖 書 ヨハネによる福音書19章38節~42節
説教題 インマヌエル、ここに極まる
讃美歌 241,273,249,25
先週のクリスマス礼拝と、夜の礼拝には、それぞれ50名を超える出席者が与えられ、改めて、私たちは、コロナ後の歩みを始めたのだなという感慨が与えられました。
またそこに集められた方たちの顔ぶれは、新しい方も多く、また、本当に久しぶりに来られた方もあり、ただ、コロナ前に戻ったのではなく、本当に新しい歩みが始まったのだと、そういう感慨が与えられました。
もちろん、日々、新しくなっていく教会の歩みのその中心には変わらないもの、いいえ、変わらないお方がいらっしゃいます。
2000年前のクリスマスに、インマヌエルという二つ名を持って、この世界に来てくださったお方、主イエス・キリストが世の終わりまで私たちと共におられる、私たち教会の主であられるというこの一点は、決して変わることがありません。
だから、教会の外面的な姿かたちは、時の経過と共に、どんどんアップデートされていったとしても、教会は教会としてのアイデンティティーを保ち続けてまいります。
そうでなければ教会は、牧師が変わる毎に、また、信徒が世代交代をする度に、別物になってしまったと言わなければならないことになります。
しかし、そうはなりません。主イエス・キリスト、このお方が共におられ、このお方が、教会において生きて働いてくださるゆえに、どんなに教会が変化をしても、たとえ、誤った道に入り込んでしまったとしても、どこまでもどこまでも、私たちと共に歩んでくださる覚悟に生きてくださる主イエスのゆえに、キリストの教会は一度も絶えることなく、2000年間、教会であり続けてきたのです。
私が牧師として仕えたこの七年間の間に、私達金沢元町教会も、少しづつ少しづつ変わってきたところがあると思います。
たとえば、目に見えるところで言えば、クリスマス礼拝が終わっても、クリスマスの飾りは、直ぐに片づけない。1/6の公現日までは、そのままにしておくということも、私が牧師になってから、しっかり定着してきたと思います。
先週も、教会外の方ですが、ある方とお話していました時に、その方は、台湾と親しい交わりがある方で、台湾では、12/25以降も、お正月を越えても、クリスマスの飾りがそのままであることを今まで不思議に思っていたと。
それは、台湾人の南の国特有のおおらかさだと思っていたけれど、私の話を聞き、謎が解けたと仰いました。
「クリスチャンが多い台湾では、クリスマスが、1/6まで続くということがきちんと意識されていたのですね」と。
だから、早く片付けなきゃと気がかりになっていたクリスマスツリーを安心して、しばらく出しっぱなしにしておきますと、付け加えられました。
けれども、数年前のクリスマスにもお話をいたしましたが、私の気持ちとしては、1/6を過ぎても、クリスマスの喜びは消えないのです。
クリスマスの喜びが、主なる神さまがこの私たちと共にいてくださることであるならば、そのことがイエス・キリストの誕生によって明らかになったと言うならば、そのお方の誕生以来、毎日がクリスマスの喜びの中なのです。
今日もインマヌエル、明日もインマヌエル、世の終わりまでインマヌエルです。
今日は12/31大晦日です。今日は、歳末主日などと言う呼び方がされることもある主の日です。
それがどれほど、教会暦の中で定着している日として定着し、意識されてきたのかは、残念ながら今回調べ切ることはできませんでした。
けれども、クリスマスの喜びの内にある降誕節の中にあって、必ず訪れる1年最後の礼拝、歳末の主日礼拝では、やはり、終わりを意識した言葉が語られる傾向があるように思います。
一日一章、365日分の聖書と短い説教を添えた良い聖書日課がいくつもありますが、私も手持ちのものをいくつか確認いたしましたが、そのほとんどが、この日に読む聖書箇所として選ぶのは、世の終わり、終末に関わる聖書の言葉か、私たちの死としての命の終わりを巡る聖書の言葉が選ばれていました。
クリスマスは光の降誕祭です。明るい輝きの中にある祝いです。真の太陽として私たちの上に昇られた主イエスの輝きを仰ぐ祭りです。
私たちキリスト教会は、その光の降誕祭が、年末を越えて、年を跨いで、1/6まで続くと意識しているのです。
けれども、同時に、その光の祝いの真ん中に、歳末主日がある。そしてそこでは、世の終わりと、また自分自身の命の終わりが、思い起こされ、意識される傾向にあるのです。
考えてみれば、不思議なことです。
期せずして、今日私たちの2023年最後の礼拝においても、私たちの命の終わりを意識することになりました。
本当に期せずして、これまでコツコツと読み進めてきたヨハネによる福音書が、主イエス・キリストの葬りを語るその場面にたまたま辿り着いたからです。
そして私は、皆さんに先立って、この聖書箇所を読み続けながら、クリスマスの真っ只中に、この世の終わり、また私たちの命の終わりを思い巡らすというのは、それは少しも不思議なことではない。違和感のあることではない。
それは、この光の降誕祭にこそ本当にふさわしいことなのだということを、教えられた思いがしています。
クリスマスのこの祝いの内でこそ、しかも、今年のクリスマスの祝い内にこそ、ヨハネによる福音書19:38以下の主イエスの葬りの出来事は、読まれるべきもの、今の私たちに与えられた聖書の言葉なのだと、つくづく感じています。
なぜ、それがふさわしいのか、今年の私たちの教会にぴったりなのか、司式者の朗読を聞きながら、既に、お気づきになっている方もいらっしゃるかもしれません。
39節の言葉です。
「そこへ、かつてある夜、イエスの元へ来たことのあるニコデモも、没薬と沈香を混ぜた物を百リトラばかり持って来た。」とあります。
かつて主イエスの元に夜陰に乗じてやってきたニコデモが、この主イエスの葬りに際して、アリマタヤのヨセフの後からやって来て、その葬りを手伝いに来たのです。
その際に、ニコデモが持ってきたものが、没薬と沈香を混ぜた物を百リトラであったというのです。
一週間前のイブの夕礼拝で、私たちが聴いた主イエスのご降誕物語にも出てきました没薬という薬、それが、この主イエスの葬りの際にも献げられたのです。
墓に葬られた身体の腐敗が少しでもゆっくりとなるように、あるいは、その腐敗臭が消され、愛する者の死が美しいものであるようにとの願いから遺体に塗られる香料、それがここでニコデモが献げた没薬と沈香の混ざった献げものです。
東方の占星術の学者達が、幼子イエス・キリストに黄金、乳香、没薬の献げものを献げたと語るのは、マタイによる福音書です。
それだから、ヨハネ福音書の著者が、ここで、クリスマス物語を思い起こしているとは言えません。
けれども、教会は、この二つの出来事、主イエスの誕生と死の重要な二つの出来事が語られる際に、福音書は違えども、それぞれの時に、没薬が献げられたという福音書の記述を深い思いで受け止めてまいりました。
東方の学者たちが幼子に献げたあの献げものの中で、既に、主イエス・キリストの死が、見つめられていたのだと。
たとえば、ルカによる福音書は、2:34のクリスマス物語の続きにおいて、幼子イエスを抱く母マリアに対して、神の人シメオンが、「御覧なさい。この子は、イスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また、反対を受けるしるしとして定められています。-あなた自身も剣で心を刺し貫かれます-多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。」(ルカ2:34-35)と、クリスマスと、主イエス・キリストの受難が一直線上にあることを初めから語っております。
主イエスが生まれた間もないそのとき、既に、このうまれて間もないやわらかな身体のこのお方から、既に、十字架の匂いが、立ち昇っているのです。
このヨハネによる福音書によって言と呼ばれるイエス・キリストは、御自分の民の所に来たのですが、民は受け入れなかったのです。
しかし、そのような逆らう民の間に、それでも肉となって宿られたという神の覚悟、神の冒険が、クリスマスなのです。
そのお方が、その最初の予感通り、その最初からの神の覚悟の通り、十字架につけられ、死んで、葬られたのです。
けれども、この出来事はただ単に、人間の罪の極みの出来事ではないのです。
自分たちの真の主人を決して受け入れることのない私たち人間のわがままが、自己中心が、罪が、このクリスマスにお生まれになった肉となった神の独り子をを殺し、死なせ、墓へ葬ったのだと言える一方で、この十字架の死と葬りこそが、父なる神様と子なる神イエス・キリストが、願い続けてきたその神の御心の完全な成就だと、さらにはっきりと言わなければなりません。
40節以下、アリマタヤのヨセフとニコデモ、「彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて亜麻布で包んだ。イエスが十字架につけられた所んは園があり、そこには、だれもまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったので、そこにイエスを納めた。」
マタイによる福音書に従うと、このまだ誰も葬られたことのない新しい墓とは、アリマタヤのヨセフ自身の墓であったと言われています。
自分がやがて入るために、用意していたその墓に、ひそかにお慕いし、従っていた主のお身体を納めたのです。
アリマタヤのヨセフも同様です。
彼が主イエスの葬りのために持ってきた没薬と沈香を混ぜた香料百リトラというのは、私たちにはなじみのない単位ですが、グラムに直すと、およそ33キログラムの香料です。
たいへんな量です。
安いものではありません。宝物と言うべき品です。
ある説教者はおそらくこれはニコデモが自分の葬りのために準備して来たものであったろうと想像します。
つまり、アリマタヤのヨセフも、ニコデモも自分の死の備えに取っていたものを差し出し切ってしまったのです。
けれども、福音書がなぜ、このような出来事を記録するかと言えば、逃げて行ってしまった情けない十二弟子とは異なり、それまでひそかに主イエスを慕い、尊敬していたアリマタヤのヨセフと、ニコデモが、恐れを突き抜けて、信仰に生き始めたということが、語りたかったからではありません。少なくとも、それが第一のことではないでしょう。
その後の教会が本当にしっかりと聴き取って来ましたように、主イエス・キリストの死は、実に、この私たち自身の死であったという恵みの事実が、ここにはっきりと見えるようにされていると、言うべきだと、私は信じています。
少しわかりにくいかもしれません。
分かりにくいようであれば、たとえば、私が洗礼準備会のテキストとして使っている雪ノ下カテキズムという信仰問答の問128の言葉を御自分の腑に落ちるまで繰り返し繰り返し読んで親しんで頂くと良いかもしれません。
そこでは、使徒信条が、十字架を語るだけでなく続けて「死にて葬られ…」としつこく語るのはなぜか?と問いながら、その理由を述べています。
少し長いですが、引用します。
なぜ、使徒信条は、「死にて葬られ」と、わざわざ語るのか?
「それは、何よりも、主イエスは本当に死なれたのだということであります。私は、使徒信条の言葉を辿ってきて、この『死にて葬られ』という言葉を読んで、ここで初めて地上における私たち自身の歩みと主イエスの歩みが一つになると思いました。それまでに主について語られてきた、その称号、誕生、み苦しみ、十字架、すべて私どものためとは言いながら、主イエスの独自の道でありました。しかし、ここでは私についても、必ず言えること、死と葬りが主イエスについて語られているのです。主イエスが真実に人間の死と葬りを共にしてくださった事実にこころを打たれます。私が死ぬときも、もはやそれは未知の世界へのひとり旅ではなくなるのです。…」
このカテキズムは言います。
主イエスのなさることは、何もかも私たちのためであるけれども、このお方の死と葬りにおいてこそ、私たちの歩みと、主イエスの歩みがぴったりと一つに重なっていることが、よくわかる。
インマヌエル、神は私たちと共におられるというお名前を持った主イエスは、この死と葬りにおいてこそ、どこまでもどこまでも、私たちと歩みを共にしてくださる方であることが事実、明らかにされているのだ。この主の御姿に心を打たれる。私は一人じゃない。私が死ぬときも、私は一人旅をするのじゃない。
主イエスの葬りにおいて起きたこと、アリマタヤのヨセフの身に起きたこと、またニコデモの身に起きたこと、それは私たちに先んじて、私たちの身に起こることの、しるしとして、まず、この二人に起きたことだったと言って良いのです。
アリマタヤのヨセフの墓に主イエスが葬られてくださったのです。ニコデモの体に塗るべき没薬が主イエスの御身体に塗られたのです。
そのようにして、主イエスは二人の死を先取りして、この者たちの死を、ご自分の死と一つにすることをお許しになったのです。
確かに主イエスを葬ったアリマタヤのヨセフの墓は、それから三日目に空になります。
ヨセフが葬られる時には、主のお身体は、その墓にはありません。
しかし、それは、一時的にでも、神の独り子は、私たちと同じように死んで葬られたので、少しは、私たち人間の死の痛みも、分かってくださるだろうという中途半端なことではありません。
むしろ、アリマタヤのヨセフは、やがて、自分も葬られることになる空になったその墓を見ながら、主のお身体が横たえられていた同じ所に、自分の身体が横たえられることを思い浮かべながら、同時に、自分の身体もまた、この場所を最後のところにするのではない。
あの朝、あのお方が、ここから出て行ったように、自分もまた、ここからやがて、出て行くことになるのだという希望に生きたのです。
使徒パウロは、第Ⅰコリント書15:12以下で、次のように述べます。
「キリストが死者の中から復活した、と宣べ伝えられているのに、あなたがたの中のある者が、死者の復活などない、と言っているのはどういうわけですか。死者の復活がなければ、キリストも復活しなかったはずです。」
このパウロの言葉には、死者の復活などはないと語るコリントの信徒に対する意図的な読み違い、聴き間違いがあると、思います。
コリントの信徒もまた、キリストの復活は信じていたのです。彼らが、信じなかったのは、自分の終わりの日の復活です。
けれども、パウロはそれを転倒して、「あなたがたが復活しないならば、キリストも復活しなかったはずだ」と、論理のすり替えのような議論をしてみせるのです。
けれども、これは、議論のすり替えでも何でもありません。キリストを信じるとは、事実、この通りなのです。
イエス・キリストはぴったりと私たちに寄り添うのです。
私たちと一つになられたのです。
そして、私たち人間の死を死なれたのです。そして、私たち人間の墓をご自分の墓とされたのです。
それによって、神の決断の事実として、アリマタヤのヨセフの墓だけではありません。ニコデモの体に塗られることになる没薬だけではありません。
ここにいる私たち一人一人の葬りを主イエス・キリストが先んじて、引き受けてくださったのであり、また、私たちが葬られることになる墓、卯辰山、金沢元町教会教会墓地、あるいは皆さんの「~家先祖代々の墓」に、あなたが葬られる前に、イエス・キリストが葬られてくださっているのです。
アリマタヤのヨセフと、ニコデモの行った主イエスの葬りの業と墓、それから、彼ら自身の葬りと墓で事実であったことが、神のまなざしにおいて、寸分たがわず、あなたの葬りと、あなたの墓に事実となっているのです。もう既に。
もう既に、先祖の誰一人として葬られていない真新しい墓であったとしても、それは、主イエスが私に先立って葬られた墓であり、私に先立って、出て行かれた墓なのです。
もしも、そのことが、この私たちの身に起こることでないならば、主イエスは甦らなかったのであり、それならば、私たちの宣べ伝えていることは、神への冒涜だと使徒パウロは言うのです。
これは、クリスマスに聴くべき神の言葉です。
光の降誕祭の只中で、私たちは私たちの死を忘れるのではなく、見つめます。
しかし、それは私たちの単独の死ではありません。私たちの単独の死などというものはもうどこにも存在しません。しかも、そこが終わりですらありません。
主イエスが共におられます、主イエスが先立っておられます。そして、墓は空になります。
私たちの生涯の、どこにもかしこにも、インマヌエルが輝いています。
最近、私はドイツの牧師であったボンヘッファーと言う人の本をちょくちょく読んでいます。
キリストの受肉、イエス・キリストがクリスマスに私たち人間と同じものになられた。私たちのきょうだいとなられたということが一体どういうことであるのか、その神学者が語る言葉に、私は深く心打たれました。
ボンヘッファーはこういう趣旨のことを言います。
キリストが、人となられたというクリスマスの秘儀は、このお方が私たちと同じ人間の苦しみを身に負われると言うだけでは十分ではない。それどころか、このお方は、現実に人間を引き受けたのだ。つまり、キリストは、わたしとあなたのすべてを引き受け、背負っているのだ。
そう言うんです。
イエス・キリスト、このお方が人となられたというのは、私たち人間の苦しみを知っているということに止まらないのです。そう言うのでは不十分なのです。
このお方が人となられたというのは、私もあなたも個にお方に完全に背負われてしまい、生きることの苦しみも、死ぬことの恐れも、もう、私個人のものではなく、このお方のものになり切ってしまっているということなのです。
私たちの死は私たちの死ではなく、このお方こそが、当事者となっている死であり、私たちの墓は私たちの墓ではなくこの方の墓であり、このお方の復活は、私たちがその後に続くための復活なのです。当事者はキリストであり、私たちは、それに従う者なのです。主の通られた道を、主に手を引かれて、命に向かって歩んで行くのです。もう、独りきりの瞬間はどこにもありません。
これ以上、ややこしいことは申しません。
しかし、最後に、もう一つだけ、私たちの信仰を語る古典的な信仰告白の言葉を引用させて頂きたい。
その言葉に載せて、私たちの告白して、今、このお方に、捧げするためです。それはハイデルベルク信仰問答の問1とその答えです。
「生きている時も、死ぬ時も、あなたのただ一つの慰めは何ですか。」
「わたしが、身も魂も、生きている時も、死ぬ時も、わたしのものではなく、わたしの真実な救い主イエス・キリストのものであることです。主は、その貴き御血潮をいもって、わたしの一切の罪のために、完全に支払って下さり、わたしを、悪魔のすべての力から、救い出し、また今も守って下さいますので、天にいますわたしの御父のみこころによらないでは、わたしの頭からは、一本の髪も落ちることはできないし、実に、すべてのことが、当然、わたしの祝福に役立つようになっているのであります。…」(竹森訳)
祈ります。
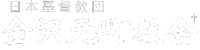

コメント