週報
説教題 目指す地へ
聖書 ヨハネによる福音書6章16節21節
讃美歌 8,290,541番(54年版)
長い夏休みを頂きまして、ほぼひと月ぶりにヨハネによる福音書の講解の続きを行います。
皆さんより一週早く、この御言葉にじっくりと耳を傾けながら、改めて、主イエス・キリストというお方と生きて行くことは、どのようなことであるか教えられた思いがしています。
今日与えられた個所は、主イエスが五つのパンと二匹の魚で、男だけで5千人、おそらく女と子どもを合わせると1万人以上の人を養い、満腹させ、なお、12のかごに残ったという奇跡を語る物語の直後の出来事です。その印象深い奇跡の後、主イエスは、ご自身を捕らえ、王にしようとした群衆を避け、12弟子をも後において、一人山に退かれました。
主イエスというお方は、一見そのように見えたとしても、私たち人間の理想通りの王、期待通りの救い主ではなかったからです。
聖書を読みながら、いつも思わされることは、私たち人間の思惑と、主イエスをお遣わしになった父なる神様のご計画は、一見、重なる部分があるようでいて、重ならないのです。
主イエス・キリスト、このお方には、私たち人間の憧れや願望をどうしようもなく搔き立てるものがありながら、決定的な部分では、このお方のありのままのあり方は、今も昔も、全く私たちが望むようなものではないのです。
それゆえ、主イエス・キリストは、御自分のことを熱狂的に受け入れながらも、誤解している者たちの願いを避け、一人山に退かれたのです。
群衆は、失望したと思います。そして、その人々の失望の延長線上には、真っ直ぐに、主の十字架への道が続いているのです。
しかしまた、この人間の誤解と失望と怒りが頂点に達したその十字架でこそ、私たち人間が心に思い浮かべることすらできなかった仕方で、真の救いの業が成し遂げられました。
十字架は私たち人間の神への失望、すなわち、罪の総体です。しかし、その最悪の罪にも関わらず、主は罪人に寄り添い続けられ、その罪の真只中で救われたのです。
さて、今日与えられました聖書箇所においても、主イエスの思いと、重なりそうでいて、ずれてしまう私たち人間の姿を、福音書記者は続けて語っているように思います。
主イエスにお従いしているようでいて、ずれて行ってしまう者達に、なお、主が寄り添う姿を語っているように思います。
物語は次のように始まります。
「夕方になったので、弟子たちは湖畔へ降りて行った。そして、舟に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。既に暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。」
5千人の給食と呼ばれる奇跡の後に、主イエスをお乗せしないままに、弟子たちが、ガリラヤ湖へと漕ぎ出して行ったという記述です。実は、この物語の流れは、ヨハネだけのものではなく、マタイとマルコにも共通しています。
マタイとマルコは、主イエスが「強いて」彼らを舟に乗せ、向こう岸に送り出したとあります。
けれども、ヨハネでは、主イエスをお乗せしないままで弟子たちの舟が漕ぎだしてしまった理由を語りません。
あえて言えば、17節後半の「既に暗くなっていた」ということが、主イエスをお乗せしないままに、漕ぎだしてしまった理由です。
それは、その日の内に、どうしても伝道の拠点であるカファルナウムに戻る予定があったということかもしれません。
あるいは、より神学的な一つの見解によれば、この暗闇とは、主イエスを見失わせる状況の象徴だと言われます。
弟子たちは、主イエスを見失うのです。夕闇の中、知らず知らずの内に、主イエス抜きで、漕ぎだしてしまうのです。
そしてそれは、群衆だけではなく、教会が、いつの間にか、主イエスを見失い、主イエスをお乗せしないままに漕ぎだし、旅路の半ばで嵐にあって、悩むことの象徴だと、学者は言うのです。
湖が荒れ始めたのは、いつ頃かはわかりませんが、場面は、岸から離れて25~30スタディオンの所です。岸から5,6キロです。ガリラヤ湖の東西は、13キロなので、ちょうど、真ん中あたりです。
その時、嵐の湖上の、弟子たちの元に、主イエスが水の上を歩いて近づいて来られるのを見たと言います。
弟子たちはそれを見て、恐れたと言います。恐怖したのです。
マタイとマルコの並行個所とは違い、ヨハネはここでもその恐怖の理由を語りません。
私たちの聴いているヨハネでは、弟子たちは幽霊だと思って恐れたわけではないのです。
名付けようもない全く得体のしれない存在として、感じられたのです。
もう一度、申します。学者たちは、この出来事が、主イエスと最初の弟子たちの間で実際に起きた出来事として福音書記者たちが理解していたとしても、同時に、これは、この福音書を読んでいる教会の姿そのものとして語っていると説明します。
そして、主イエスと12弟子たちの、かつての姿に、今の自分たちの姿を重ね合わせて理解する傾向は、ヨハネによる福音書が、最も強いと言われます。
つまり、この福音書は、今日この物語を耳にした私たちが、この弟子たちと主イエスの姿を、この私たちと主の姿として、聴くように、迫っているのです。
十字架とご復活前の、まだ成熟していない無知な弟子たちの姿として、自分たちとは違う者としてこの出来事と距離を保つことはできません。
主イエスの十字架とご復活によって生み出された教会、聖霊を送られている教会の鏡として、この出来事に耳を傾けるように、迫られているのです。
すなわち、他の誰でもない私たちが、夕闇の中で主イエスを見失い、知らず知らずの内に、主を置いて漕ぎだしてしまっているのです。
その途中で嵐にあい、助けを求め、自分たちの内を主を探し回っても、主イエスの御姿をどこにも見出せないという経験を私たちがするのです。
そのような私たちを見捨てず、湖の上を歩いて追いかけて来られた主を見つけると、その近づいてきてくださった方がどなたであるか全く理解せず、恐れ惑う私たちなのです。
自分の願望や理想を主イエスに投影し、熱心になったり、失望したりするのは、1万人という無数の群衆だけではありません。
弟子たちにとっても、教会にとっても、時に、主イエスは、自分たちの舟の内ではなく、外から来る、荒れた湖を踏みしめながらやって来る得体のしれない恐ろしいお方なのです。
カトリックの作家、小川国男は聖書のことを「襲いかかる聖書」と言いました。
それは、生きているのです。今日の箇所で証しされるような生きたイエス・キリスト、私たちの自由にはならない生けるイエス・キリストを証しするものなのです。
もちろん、私たち教会は、主イエスを愛しております。この方にお従いしたい。この方と共に歩みたいと心から願っています。
けれども、私たちは弱い者です。
はっきり見えていたはずの主イエスの姿が、夕闇の中に見失ってしまうのです。全く意図せず、知らず知らずの内に、主イエスをお乗せしないまま、舟を漕ぎだしてしまうのです。
教会という舟が、信仰の船が、主イエスをお乗せしないままに、もう出航してしまい、湖のど真ん中まで進んでしまい、嵐に漕ぎ悩み、進むことも、戻ることも叶わなくなり、その上、主イエスのご不在に今更気付いた絶望状況に陥るのです。
しかし、主イエスはそのような舟をお見捨てになりません。主イエスをお乗せせず、漕ぎだしてしまった罪深い弟子たちをお見捨てになりません。主イエスをお乗せしていないゆえに、もはや、主の者たちとすら言えないような深みまで漕ぎだして進退窮まった弟子たちをお見捨てになりません。
嵐の湖を踏みしめて、迎えに来られるのです。
その姿を見て恐れたという弟子たちの姿は、本当の主イエスが近寄って来てくださっているのに、得体のしれない者としか見れなくなってしまっている教会の姿です。福音書記者ヨハネはそう読まれることを望んでいます。ヨハネ自身が、自分のこととしてそう読んでいます。
やがて、ヨハネの教会は、信仰理解を巡って、主イエスをどのようなお方と理解するかを巡って、分裂の危機に瀕したと言われます。
主イエスが、よく知った方ではなく、見知らぬ方になってしまっている。主が全く見知らぬ方であるかのように、いいえ、それ以上に、自分を脅かす敵であるかのように、恐れるのです。
けれども、どのように恐ろしい者に見えたとしても、どんなに自分達を脅かす存在に見えたとしても、本物の主イエスは、20節、「わたしだ。恐れることはない。」と、真の福音を語るのです。
恐ろしい嵐の只中から、恐れの中心から、良き知らせが聴こえてきます。「わたしだ。恐れることはない。」
「わたしだ」とは、聖書において、特にヨハネにとって、特別な言葉です。
旧約で、神がモーセに自己紹介された、神さまの自己紹介の言葉そのものです。「わたしだ」、「わたしはあってあるものだ」、「わたしはあるというものだ」。
旧約において謎めいたこの神のさまの自己紹介の言葉は、主イエス・キリストというお方においては、謎でも何でもありません。
主イエスにおいて、「わたしだ」という神様の自己紹介の言葉は、激しい慰めの言葉、深い深い福音の言葉であることが、明らかになります。
「わたしだ。恐れることはない。」
わたしだ。このわたしだ。あなたたちを迎えに来た私だ。あなたたちを一人にしない私だ。進むことも戻ることもできないあなたたちのために、私の方からあなたたちの元に歩み寄るわたしだ。あなたたちはわたしを恐れる必要はないのだ。
だから、ある人は、言います。
この20節の主イエスの温かい御言葉、「わたしだ。恐れることはない。」とは、「インマヌエル」ということ、あなたがた共にいる私、世の終わりまで、いつも私たちと共におられる神の自己紹介の言葉だと。
インマヌエル、神はわれわれと共にいます。主を忘れ、主を乗せず、取り返しのつかない地点までずんずん進んでしまい、助けに来られた主を見分けられず、主を得体のしれない敵と見做し恐れてしまう、罪人なる私たちと共にいます。
「わたしだ。恐れることはない。」
わたしだ。わたしなんだ。あなたがたと共にいるために、あなたがたを孤独にしないために、追いかけてきたわたしなんだ。身を固くしないでほしい。恐れないでほしい。
21節にこうあります。恐れる弟子たちが、この主の言葉を聴いて、正気に立ち返った時、「そこで、彼らはイエスを舟に迎え入れようとした。すると間もなく、舟は目指す地に着いた。」
私たち教会の象徴たる舟に乗った弟子たちは、湖の上を歩いて来られた得体のしれない方が、自分たちを迎えに来られた主であることを知ると、舟に迎え入れようとしました。正気に立ち返り、主と出会い直し、自分たちの舟に乗ってもらおうとしました。しかし、福音書は主がそ舟に乗り込めたか、どうかはっきりとは書きません。むしろ、「すると間もなく、舟は目指す地に着いた。」と、主を舟の中にもう一度迎え入れるためにバタバタとしている内に、目的地に着いてしまったことを仄めかしているように見えます。
実は、この記述も、ヨハネによる福音書独特のものです。マタイとマルコでは、主イエスはすぐに舟に乗り込まれるのです。けれども、ヨハネでは、弟子たちの舟に乗り込んだのか、乗り込まなかったのか定かでない。
そうこうする内に目的地に着いてしまったというヨハネの記述は、私たち教会にとっては、情けなく、主に申し訳ないことであることには違いありませんが、たいへん慰め深いことであるとも思います。
この出来事の始まりが、湖の真ん中で起きたことを重んじるならば、その御言葉によって主だと弟子たちが気付いた後も、残り半分の道のりを通して、主をお乗せしようと励んでいる内に、着いてしまったのです。つまり、お乗せしようと動き出してからも、なかなかお乗せすることができなかったのです。
これが教会のことであるならば、ヨハネの教会自身が、悩み、苦しんでいたのだと思います。主をお乗せしていないことに気付いた後も、主の慰めの御言葉を聴き、はっきりと主を主と見定めることができるようになった後も、なかなか主をお乗せしていると自信を持って言うことができなかったのです。けれども、その弟子たちの舟は、主イエスと共に、目的地に着きました。
私たち教会の歩みというものがもしもこのようなものであるならば、それは大変心許なく、情けなく、教会に加わっていない、この世の者たちの歩みとどこが違うのかと、戸惑うかもしれません。
私は私の人生の舟の中にしっかりと主イエスをお迎えしていると、胸を張って言えるのが、キリスト者であり、教会であると考えるかもしれません。実際、マタイとマルコは、追いかけて来られ、再び、教会である弟子たちの舟に乗り込んでくださる主イエスであることを証ししたのです。けれども、私は、ヨハネによる福音書が象徴的に描く、この舟の姿、教会の姿もまた、実に、教会らしい姿であると思います。
一体、教会とは何であるのか?主イエスと同じ舟に乗るものなのか?むしろ、道を外れて行く者たちを、主を見失っていく者たちを、どこまでもどこまでも追いかけて来られ、主に寄り添われている心許ない小舟が教会ではないのか?教会が教会であるのは、主が捨てず、主が共にいることを決意してくださっている、このことだけに拠ると、私はヨハネと共に信じます。その時、私たち教会の証は、キリストをご紹介する言葉は、新しい響きを立て始めるのではないかと思います。
先に主を受けいれた者が、まだ主を受け入れていない者に、信仰の決断を迫る、上から目線のものではなくなると思います。「わたしだ。恐れることはない。」という言葉に、目を覚まして頂き安堵した者が、同船する仲間の肩を叩きながら、荒れる湖に立つ主イエスを指差しながら、「あれは私たちの主だ。私たちの救い主だ。あなたの主が共におられる。大丈夫だ。」と、語りかける言葉以外ではなくなるのではないかと思います。
5千人の給食の後に、主を誤解した人々から身をかわし、山に一人退かれた主イエスが、その人々をお見捨てになったのではなく、むしろ、真っ直ぐに、過越しの小羊として、十字架への道を歩まれたように、主は主をお乗せしていない舟を追いかけて来られ、寄り添われるのです。
インマヌエル、主は私たちと共におられます。
昨日、教会員の赤尾さんが召されました。三日前より急激に体調が悪化したとご連絡を受けました。ちょうど、今日の説教準備をしている最中でした。20節の言葉がインマヌエル、神共にいます主の約束の言葉だと学びながら、赤尾さんのことを思い出していました。赤尾さんは、懇意にしていたある聖書学者から次のことを学んだと私に語って聞かせてくださったことがあります。
マタイによる福音書10:29の「二羽の雀が一アサリオンで売られているではないか。だが、その一羽さえ、あなたがたの父のお許しがなければ、地に落ちることはない。」この「父のお許しがなければ」という主の御言葉、これは、原語では、単純に「父なしでは」という言葉なんだ。つまり、一羽の雀が地に落ちるその時、それは天の父のご計画の内にあるどころか、天の父が、雀と一緒に地に落ちて行かれるのだ。そう理解できると教えて下さいました。
赤尾さんからその解釈を聴いて以来、私の心の奥深くにもしっかりと刻まれて、忘れることのできない聖書の読み方になりました。地に落ちる一羽の雀に寄り添う主は、嵐に漕ぎ悩む私たちを追いかけ、その舟にどこまでもどこまでも寄り添ってくださるのです。
その主の憐みのゆえに、私たちの歩みは、どこまで行っても貧しく、不器用で、欠け多く、罪深いものであったとしても、必ず、目的地まで導かれていくのです。主が私たちを見捨てず、私たちと共におられるからです。主の御名は誉むべきかな。
祈ります。
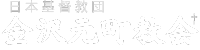
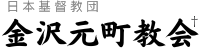
コメント