ヨハネによる福音書1章1節~5節
既に、一か月前に予告しましたように、今日からヨハネによる福音書を聞いて行きます。これから毎週毎週この福音書を読んでいきますが、読み終えるためには数年かかると思います。
この福音書は第四福音書と呼ばれています。四つの福音書の最後に置かれているからそういう呼び方をするのは、当たり前とも言えますが、たとえば、マタイによる福音書を第一福音書などという呼び方はあまりしないのではないかと思います。
むしろ、最初の三つの福音書は、まとめて共観福音書と呼ぶのが常識的な呼び方であります。三つの共観福音書と、第四福音書です。
共観という言葉は、「共に観る」と書きます。それぞれの福音書にはそれぞれの個性がありますが、記録された事件や、主イエスの言葉など、最初の三つの福音書には、共通している部分が多いのです。
けれども、4番目に置かれたヨハネによる福音書は、この福音書にしか記録していない事件や主イエスの言葉だらけなのです。
この福音書は一番最後に書かれたものと考えられています。他の三つの福音書とはだいぶ違う材料が使われています。だから、この福音書には、かなり脚色があるのではないか、信頼に足る福音書ではないのではないかと考える人もあるかもしれません。
しかし、その独自の材料は、最終章の21:20などに登場する「イエスの愛しておられた弟子」に由来するものと考えられています。この福音書の中で度々主の一番弟子ペトロと対比される主の愛弟子です。
伝統的にはゼベダイの子ヨハネと考えられてきました。多くの学者は、そのことに否定的であり、この愛弟子を「無名の弟子」としますが、東京神学大学の学長を務めた松永希久夫先生は、使徒ヨハネである可能性は高いと言います。いづれにせよ、この独自なヨハネによる福音書もまた、主イエスの生きた証人の証言によるものだと考えて間違いありません。
さて、このヨハネによる福音書の冒頭は、既に、他の福音書とは全く違うものになっています。もう少し視野を広げると、他の福音書どころか、聖書66巻中でも、似たようなものがない特殊なスタイルで書かれていると言えるでしょう。
「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。」
これまでも多くの人たちが指摘してきましたが、ギリシア哲学の影響があるのではないかと考えられています。
けれども、近年多くの学者が共通して言います。確かに、この福音書の冒頭は、ギリシア哲学の中で用いられているような用語を使うが、ヨハネは当時の常識的な使い方も、学問的使い方にも、ほとんど頓着していない。自分の使いたいように使っているということだそうです。
それならば、この変わった書き出しは何なのか?この1:1-18のヨハネのプロローグは賛歌だと言います。難しい哲学の言葉でも何でもない。既に教会で歌われていた賛美歌が元になった言葉だと言います。
教会のみんながよく知っている賛美歌を材料に、その歌に声を合わせ、キリストの恵みを思い起こしながら、もっと豊かに歌い出す。そういう言葉だと言うのです。
なるほど、私たちの普段着の言葉とは違うから、不思議に思えるヨハネによる福音書の書き出しは、哲学の難しい言葉だからじゃなくて、賛美歌のしゃれた言葉だから、こんな書き方になるのです。
「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。この言は、初めに神と共にあった。」
あんまりこういうことは、聖書に対して言わないかもしれませんが、おしゃれですね。かっこいいですね。確かに日本語で朗読しても、詩的な感じがしますね。
丁寧なことを言えば、このヨハネのプロローグは、どこが元々あった賛美歌で、どこが福音書記者の言葉か、細かい研究があるようですが、今日は、ざっくりと、この全体を賛美歌の歌詞と表現しておこうと思います。
この歌の出だし、あまり、丁寧に検討しなくても、一読しただけで、これを歌っている人は、なんて、言葉を重んじている人だろうと思います。歌ったのは個人ではなく、教会ならば、こんなことを語り合う集団は、なんて言葉に対する厚い信頼を持っているのだろうと思います。
私たち現代人の常識的な感覚、一般的な感覚からするとどうでしょうか?言葉って何か軽いものだなと思っているところがあります。
言葉はなくてはならないものですし、一つの言葉によって救われるという経験も、皆したことがあるでしょうが、それと同じだけ、言葉に苦しめられてきたと思います。
言葉によって救われて、言葉によって傷つけられて、言葉は裏腹なものです。
特に言葉を厄介に思うのは、言葉と、伝えたいことが必ずしも一致しないということです。それは何も、悪意を持って本音と建て前を使い分けることができるから、言葉は厄介だというのではありません。
それ以上に、言葉の厄介さは、どんなに言葉を尽くしても、自分の伝えたいことは伝えきることができないと感じられることです。むしろ、言葉を足せば足すほど、どんどんどんどん伝わらなくなっていくということが、起こることがあることです。かと言って、無口でいると、不機嫌なのではないか、気に入らないことがあるのではないかと、裏の意図があるように読み込まれてしまうことです。
そんな時、私は、もしも、自分の胸を切り開き、心を取り出して見せて、それを見てもらえばそのままに伝わるのならば、その方がずっといいのになと思うことがあります。
言葉というものは、なんて不自由なのだろうと思うことがあります。言葉なんてなければいいのにと、思うことがあります。
だから、私たちの文化の中には、「百聞は一見に如かず」という言葉があります。また「言うは易し、行なうは難し」という言葉があります。同じように「不言実行」という言葉があります。
言葉は、有名無実になり得るから、行いの結ぶ実の方が確かであると、そう考えることが、しばしばあります。
私たちのこの自分の心をありのままに表現するのにも、言葉は不自由です。まして、神の恵みの素晴らしさを語るのに、言葉は足りないものだと言わなければならないと思います。
だから、もしも、神の恵みを大きさに心打たれながら、私たちが賛美歌を歌い始めるならば、「言葉を越えた神の恵み、言葉にならない神の恵みの大きさ」と、歌い始めるのが良いように思います。
ところが、ヨハネによる福音書は違います。
「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。」と歌い出します。この福音書には言葉への深い信頼があります。いいえ、この福音書に限らず、聖書は、簡単に、筆舌に尽くしがたいなんて、逃げないんです。言葉では言い尽くせない神の恵みを、言葉で言い表すのがもどかしく感じるような神との出会いの経験を、自分の貧しい言葉では言い尽くせないことを重々承知の上で、それでも、限界のぎりぎりまで何とか言葉にしようとするのです。そういう言葉への深い信頼があるのです。
なぜならば、この出だしの言葉、「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。この言は、初めに神と共にあった。」と歌わずにはおれない、私たちの神さまと言葉との間の、私達にも告げられ、知らされた、両者の深い親密さがあるからです。
「初めに言があった。」
この「言」と読まれている言葉、よく観察してみると、「葉」という文字が抜けています。聖書を読んでいる人には、もう慣れっこになって違和感を覚えないかもしれませんが、「言」うという一字で、コトバと読ませています。文語訳聖書からそうです。不思議な書き方です。
何でそうなっているか?その理由をはっきり聴いたことはありません。しかし、ローマ・カトリックの押田成人神父は、古い日本語において、言葉の「コト」と、出来事の「コト」は、本来一つのものであったと言うのを読んで、ここにヒントがあるかなあと思ったことがあります。
元々、言葉は、言葉だけってことはない。元々言葉の裏には出来事がある。出来事があって、言葉として発せられる。体験、経験、出来事から言葉が生まれる。ちょっと、大雑把ですけれども、元来、言葉と出来事はセットである。それを押田神父は、「コト言葉」という言い方で、今や私たちの周りにたくさん溢れている抽象的な言葉とは分けます。
抽象的、理念的言葉がいけないんじゃなくて、元々の言葉というものには、有名無実などということはあり得ない、「言うは易し、行なうは難し」なんていうものではない。出来事と言葉は一つのものなのです。
ちょっとだけ脇道に逸れますが、やがて、時代が下って来て、世の中が複雑になって、言葉による抽象化が必要にされて行った時、それまでは一つであった出来事と言葉を分けるために、「コト」に切れ端を意味する「ハ」を足して、言葉となったと考えられるようです。しかし、そうなるとどんどん言葉のインフレが起こり、有名無実ということが起こってくる。
元に戻りますが、実は、日本語だけでなくて、旧約の書かれたヘブライ語も同じ事情なんです。
旧約で「言葉」と訳されるダーバールという単語は、「出来事」とも訳されます。日本語と同じなのです。
いい加減なことは言えませんが、これが、ヨハネの冒頭で、「言」という一字でコトバと読ませる理由ではないかと思います。少なくとも、そのことを思い起こさせる訳し方です。
つまり、ヨハネによる福音書のことの冒頭の初めにあった「言」というのは、ギリシア哲学的な、宇宙の理念とか、宇宙法則とか、ぜんぜんそういうものではないのです。もっと手応えがあります。実体があります。
一人の人がキリスト者になると言うのは、まさにその実体に出会ったからです。一つの教会が生まれるというのは、まさにその実体に出会ったからです。それも言葉において、この実体と出会うのです。宣教の言葉において、そしてまた、一度限りの洗礼、何度も繰り返す聖餐という見える言葉において、実体を持つ言葉と出会ったからです。
だから、賛歌です。賛美です。こねくり回した抽象的な思弁なんてものではありません。喜びが溢れ出して、歌となって言葉となるのです。
この手応えのある言は、次回扱う14節で、それこそ、はっきりコトバ化されますが、肉となった言、イエス・キリストのことであることが明かされます。けれども、多分14節で初めて明らかになるわけでもありません。
実は、2節に「この言は」とありますが、既にここを「彼は」と訳す翻訳があります。日本語では、「言」という訳が、冒頭部分で10回以上出てきますが、原語では二回だけです。あとは、代名詞だけです。その代名詞を、「彼」と訳すことも十分に可能なのです。
それを元に、「初めに言があった。彼は神と共にあった。彼は神であった」と訳すことができる。そして、これを聴けば、キリスト者ならば誰でもすぐに、当然、この「彼」とは、イエス・キリストのことだとわかるのです。
しかし、それならば、なぜ、最初から、「イエス・キリスト」と言わなかったのか?ギリシア人に伝える伝道的意図をもってという説明もされてきましたが、創世記との関りも大きいかもしれません。
多くの学者が、このヨハネの冒頭が、創世記冒頭の世界創造の物語を意識しているだろうと、考えています。
その言葉によって、世界を創造された神の物語です。「光あれ」と神が仰ると、無、あるいは混沌から光が生じるのです。力ある神の言葉です。ここに見られる神の言葉は、ここまでで確認しましたように、言葉と出来事が100パーセント一致している出来事の言葉です。
ヨハネによる福音書は、主イエス・キリストこそが、この神の言そのものだというのです。神の言によって造られるものではなく、万物を造り出す神の言そのもの、初めから神と共にある、神と並ぶ神である言だと言うのです。ものすごい先取りになってしまいますが、ご復活のイエスさまとの出会いの出来事は、出会った者に「わたしの主、わたしの神よ」という言葉をもたらします。
そして、創世記の記述だけからすれば、非常に驚くべきことを語りますが、そうであるならば、こういう出会いを与えられた者は、当然、3節、「万物は彼によって成った。成ったもので、彼によらずに成ったものは何一つなかった」と言わざるを得ません。
つまり、世界創造は、父なる神が、言なる神であるイエス・キリストによって行ったと歌わざるを得なかったのです。私は今回、この箇所の学びをする中で、度肝を抜かれたことの一つはこれです。御子による世界創造です。
もちろん、三位一体の神として、子なる神が、世界創造にも協力しているという理解は持っていました。けれども、こんな風には、理解していませんでした。御子は創造にも手を貸しておられたどころじゃないんです。
創世記が語る通り、神の言が、万物を造ったということは、新約から理解するならば、万物は、御子によって成った。御子によらずに成ったものは一つもないということになるのです。
私は今も、興奮が冷めませんが、このことを通して、天地の創造というのが、神の愛の業であることがはっきりわかった気がします。
私たちのために十字架にお架かりになったイエスさまが、一生懸命に、言わば、その手ずから人間をお造りになった。人間だけではなく、万物をお造りになった。
世界創造の出来事の中に、既に、御子によって露わになる神の愛が、丸ごと籠められている。しかも、これは、ちょっと思い出してみれば、ヨハネによる福音書の冒頭に書かれているだけではありません。コロサイ書1:10や、ヘブライ人への手紙1:2にも、御子による天地創造が語られています。父のお手伝いではなく、父なる神の「御子による創造」が語られています。
天の父の言であるイエスさまの愛が世界を造っている。天の父の言であるイエスさまの愛が万物を保っている。
天地の造り主なる父なる神様とは、自分では気づかずとも、誰もが、創造主と被造物という関係で関わっているかもしれない。けれども、教会の説教を聴いて、イエスさまの十字架による罪の赦しを受け入れない限り、人間はイエスさまと何の関係もないと思うことはできないのです。
命が保たれているということで、父なる神様からの恵みは、どんな者でも頂けるけど、十字架を受け入れない限り、イエスさまの恵みとは、何の関係ないということはあり得ないのです。
御子に造られているんです。成ったものの内で、御子によらないものは一つもないのです。御子こそ命の源です。天地創造以来、ずっと御子こそ、人間の光なのです。父なる神と共に、ずっとずっと御子に支えられてきた世界です。
最後の5節の言葉は、これから始まるヨハネによる福音書全体の結論を先取りする言葉であると思います。
「光は暗闇の中に輝いている。暗闇は光に勝たなかった。」
今の朗読、おやっと思われたかもしれません。5節の後半を、新共同訳ではなく、新しい聖書協会訳で読みました。
これからのスタンダードになる新しい訳では、「暗闇は光を理解しなかった」ではなく、「闇は光に勝たなかった」です。
原語を直訳すると、「暗闇は光に追いつかなかった」です。
5節に突然語られる暗闇、創世記の創造前の混沌を覆っていた闇を思わせる暗闇です。
父が御子によって造られた万物をもう一度、混沌と虚無に還そうとする力を象徴するような闇です。
けれども、この暗闇の中に光が輝くのです。光を決して理解しない闇、神の創造を台無しにしようとするどこからともなく現れた闇の力。
けれども、この闇の力は追いつかないのです。その恐ろしい虚無の力を奮っても奮っても、追いつかない。対応できない。手が回らない。光を押しつぶそうとする闇の失敗を語ります。
創造の神の言と呼ばれる「彼」が、「光」が、「人の命」が、人となられた御子が、世界を覆わんとする闇と混沌の中で、再創造をお始めになるからです。
最後にもう一度申しますが、これは賛歌です。思弁ではありません。イエス・キリストという出来事にぶつかり、その生きたご人格にぶつかり、十字架とご復活の福音にぶつかり、生ける言にぶつかり、生まれ出た讃えの歌である言葉です。
このぶつかって来たお方が、ぶつけられた者を動かしている。ぶつけられた者を変えてしまっている。揺り動かされた者の、揺り動かされた言葉を語っている。
私は、昨晩、夢を見ました。夕闇の中、教会の前を一人歩いています。そこに、ある教会員からラインが入ります。「私は主によって、今日、相生を教わった。この世界には相生の余地があるんですね。」
相生なんて、あまり耳にしない言葉です。「人と人とが相共に生きる」という意味の言葉です。この言葉自体は知っていました。しかし、私にとって親しい言葉ではありません。今まで自分では使ったことがありませんでした。
けれども、昨晩、そんな夢を見ました。そして、目覚めて、しっくり来ました。
ヨハネは相生を歌っている。私と共に生きてくださる主イエスとの相生、造られたすべての物を生かそうと共に生きてくださる主イエスの相生、未来のことではなく、理念のことではなく、今ここで、福音書記者の身に、その人の属する教会に、そして、万物に、この相生が始まってる。人となられたキリストが共に生きてくださる。
この再創造の言葉が、今も響いています。ここに響いています。言と呼ばれる「彼」は、ご自分の造られたすべてのものを、再創造されます。この方は御自分の造られたものをお忘れになりません。この方が目を離している内に、この方のあずかり知らぬ内に、父がお一人でお造りになったものは、一つもありません。万物に責任を持たれます。
どんなに闇の力が覆おうとしても、この方は、私たちを造り直すことがおできになる、万物は、この方と共に生きるのです。
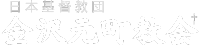
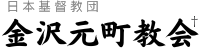
コメント