11月29日 コリントの信徒への手紙二3章4節から11節
主を待ち望むアドヴェントとなりました。今日からクリスマスまでの間、主イエス・キリストのお誕生日の祝いを今か今かと待つだけではなく、やがて、その方が再び裁き主として来られる再臨の思いを新たに待ち望む時を過ごします。
しかし、あまり再臨ということは、私たちが信仰者であっても、そんなに強く意識していないことかもしれません。アドヴェントはクリスマスを待ち望むばかりの季節になってしまっているかもしれません。けれども、日本語では、待降節、待ち望む季節と表現しますが、元の意味では、アドヴェントは進軍、軍隊の前進という意味があります。そうすると、2000年前のお誕生日に思いを馳せるよりも、実は、再臨にこそ、ぴったり来る表現であるかもしれません。というのも、今日も告白した使徒信条が語るように、やがて再び来られる主イエスとは、「かしこより来りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん」審判者であられるからです。だから、待降節を過ごす思いというのは、ただめでたいばかりではなく、身の引き締まる思いをも抱かせるものだと思います。主イエスが再び来られる日には、神の最後の審判が下されるからです。
しかし、だからといって主イエスの再臨と、その審判を意識するこのアドヴェントに整えられていく、私たちの心というのは、最初のクリスマスの出来事を巡るザカリア、マリア、羊飼い、ヘロデに生じたような不安と恐怖に終わるものではないでしょう。最後の審判を待つアドヴェントに備える私たちの心は、クリスマスから復活に至るまでの、御子イエス・キリストが既に歩み通してくださった歩みに縋ることができるものだからです。
そしてそこで御子のゆえに神が私たちの内に作ってくださる心とは、今日の個所でパウロが語るような、神の御前で抱くことができる、私たちの確信だと思います。神の御前でおどおどしない。確信を持って立つことができる。だから、当然、審判の前でもおどおどすることはないのです。
聖書は、複数の個所で信仰者の姿を大胆な者として描きます。たとえば、エフェソの信徒への手紙3:12で、「わたしたちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により、確信をもって、大胆に神に近づくことができます。」と言われています。ここでは、今日の個所よりもよりはっきりと伝道者だけではなく、全てのキリスト者の特質として、神の御前での大胆さ、恐れなく何でもお話しできる率直さ、神の御前での確信を抱くことができること、これは、キリスト者の特質であると、語っているようです。このような大胆な者、確信を抱く者として信仰者の姿を描くのは、パウロだけでなく、聖書のところどころから、聴き取ることのできる言葉であると思います。確信という言葉、信頼とも訳せます。神の御前に自分は立つことができるという確信、神の御前に自分はびくびくする必要はないという信頼を抱ける。他の誰でもなく、この私たちが抱くことができる確信です。
しかし、考えてみれば、これは、なかなか傲慢なようにも思います。神様の御前に、自分は立てるんだなどと、胸を張って言うことができる人間というのは、主イエスが退けた最悪の人間の姿ではないだろうかと私などは思います。主イエスが教えてくださった私たちの神様は、ルカによる福音書18:11以下において、「神様、わたしはほかの人たちのように、奪い取る者、不正な者、姦通を犯す者でなく、また、この徴税人のような者でもないことを感謝します。」と胸を張って自分の正しさを神に差し出すことのできた、自分は正しい者であると己惚れていたファリサイ人を退け、代わりに、目を天に上げようともせず、胸を打ち叩きながら、「神様、罪人のわたしを憐れんでください。」と祈らざるを得なかった、徴税人をこそ、正しい者だと呼んでくださるお方です。
それなのに、神さまの御前に自分は立つことができると確信を持つことができると言いだした、パウロと、後の教会は、地上を歩まれた主イエス・キリストの実際の教えからは、遠ざかってしまい、ここでまた、新たな宗教エリート主義を復活させようとしているというのでしょうか?
このような主イエスの離反から、教会がまた再び、神は罪人をこそ、心くずおれる者をこそ、支えて立たせてくださるお方であることを、再発見するには、「絵空事の罪人ではなく、本物の罪人になれ」、「罪人にして、同時に義人」と、語った改革者ルターまで待たなければならなかったことでしょうか?
もちろん、そんなことはありません。パウロが語り、他の聖書記者も語る、神の御前に確信を抱ける者、神の御前にしっかりと両足で立つことができる者、びくびくおどおどしなくても良い大胆で率直な者とは、他の誰もなく、パウロであり、私たちでもありますが、しかし、そこでパウロが抱くことができると語る確信は、自己信頼、自己確信と似て、非なるものです。
神の御前にあって、自分を信頼する道でもなければ、不安に苛まれる道でもない道があります。というよりも、今は、その道以外は残されていないという道があります。それは、キリストによって神の御前に立つという道です。私たちを神の御前に立つことができるようにするのは、ただイエス様によることです。パウロが、「わたしたちは、キリストによってこのような確信を神の御前で抱いています。」と語る通りです。「キリストによって」という言葉が、とても大切です。信仰のはじまりも、半ばも、終わりも、イエス様抜きで、神の御前に立てる瞬間と言うのは、訪れないのです。もしも、このことを忘れ、「独りで何かできるなどと」思い出したら、私たちは途端にファリサイ人になります。律法主義者になります。
神さまは私たち人間に、御前に立つ資格、大胆に率直に神さまに近づき、天の神様のことを、私の父、私は神様の子どもですと言えるほどの資格を与えてくださっています。けれども、この資格は、運転免許のようなものではありません。運転免許は、たとえ、うっかり家に置いてきても、免許不携帯の減点で済みます。それによって、運転する技能が疑われるわけではありません。きちんと教習所に通い、運転の知識と技能を身に付け、試験をパスして、免許証を取得したのです。その免許は、その条件をクリアして、ふさわしい者に、与えられた太鼓判と許可です。だから、逆に言えば、その条件を満たさなくなれば、自分の側の変化により、取り上げられたり、返納する必要の生じるものです。
けれども、天の神様の御前に立つ資格は、こういう資格とは異なります。資格発効の条件は、私たち人間の側で整えられるものではなく、「キリストによって」、すなわち、神さまご自身がイエス・キリストを通して、イエスさまのできごとを通して、私たちのために準備してくださることによってのみ整います。資格は、ただ、神さまが恵みとして与えてくださるものです。独りで何かできる、まして、独りで神さまの御前に立てるなどということはあり得ないことです。
先日、金沢教会を会場として、二人の伝道者の按手礼式が行われ、この金沢にまた、二人の牧師が誕生しました。神学校を卒業してから最低三年、教会の教師として仕え、試験を受けます。それに合格し、牧師としての備えができたと認められて、按手を受けることができました。牧師になると、伝道師の頃は許されなかった、洗礼と聖餐の聖礼典を執り行うことができるようになります。けれども、間違ってはならないのは、按手を受けて牧師になれば、その人は、いつでも自由に洗礼と聖餐を執行できる条件を満たしているということではありません。つまり、牧師の資格を得れば、好むままに、洗礼を授けたり、聖餐を執り行えるのではありません。そういう権限は、日本基督教団の牧師にはありません。実は、その権限を持つのは牧師ではなく教会であり、具体的には、教会総会によって選ばれた長老会の決定に基づき、執り行われるのです。しかし、それは牧師個人ではなく、教会に属する大多数の多数決による民主的な権利というわけではなく、教会がキリストの体と呼ばれることと関係のあることです。キリストが聖礼典の権限を御自分の体である教会に任せられる。そのキリストの意思を教会総会で選ばれた長老会の決定の中に見ようと私たちは、信仰の決断において決めています。その際に、日本基督教団に属する教会は、按手を受けた牧師がそれを執行すると、決めています。だから、牧師になるまで、聖礼典を行うことができないだけです。もしも、単立教会であったり、別の教団であれば、まだ牧師の試験に合格していない伝道師でも、あるいは、牧師がいない場合は、信徒が聖餐の司式を行うと決定しても、構わないのです。しかし、それは誰でも、資格なしに、自由に聖礼典を執行して良いということではありません。教会の許可があるならば、その背後に、神さまのお許しがあるならば、可能だということ、資格はその神さまの許可によって与えられるものであって、それを実際に執行する人間自身に備わっているわけではないということです。この牧師理解については、別の意見を持っている人もいるでしょうが、少なくとも、パウロが神の御前に立つ資格ということに関しては、今申し上げたことと似ていると思います。
自分が自由自在にできる資格ではなく、ただ、キリストのゆえに、神さまに許可されて立つことができるということです。
このように申し上げると、神の御前に立てる私たちの資格というのは、心許ない資格のように思われるかもしれません。自分の側には、それを満たす条件は整わず、ずっと、恵みと憐みによって許可され続けることを必要としているならば、旧約の王妃エステルのように、王の庭に侵入するのは、その都度、命がけということになってしまいます。
もちろん、神さまにはその自由があります。しかも、主イエス・キリストの父なる神さまが、その恵みと憐みに変えて、裁きを下される時、私たちはなんて勝手気ままな神さまだと言うことはできず、自分達の罪の報いにふさわしい報いを受けているだけで、文句を言うことによって、いよいよ私たちは自分が神に生まれながらに敵対する罪人であることを露わにするだけであると言わなければならないでしょう。けれども、この神の自由は、私たちの不確かさよりも、確かな自由です。
なぜならば、神様が私たちにお与えになると約束された御前に立つ資格は、神御自身からその御手ずから石に刻まれた、私たちには変更不可能と思われる律法による古い契約、すなわち、神のくださる恵みにふさわしく、神に従って生きるようにという、当り前の神と人間の相互契約を塗り替えて、神に逆らう罪人に恵みを与え続けることによって生かすという一方的な恵みの契約を結び直してくださったからです。古い契約、律法の契約も、神さまの素晴らしい契約です。人間には命を、神さまには、服従を。神さまは服従しても、正当な報酬を下さらない残酷な主人ではなく、働きに応じて、服従に応じて、正当に報いてくださる主人であるというのは、有難いことです。しかも、神様は、実を結ぶまでは、報酬を与えないというのではありません。
十戒の冒頭にあるように、「わたしは主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である」から、私に従ってほしいと、仰るのです。服従が先で、恵みが後ではありません。恵みが先で、服従が後です。そのような契約を告げ知らせ、神さまに精一杯お仕えすることを勧めるモーセの働きは、輝かしいものです。けれども、人間はその徹底的な弱さのゆえに、神との相互契約にお仕えし切ることはできませんでした。服従の義務を果たすことはできませんでした。どこでどう捻じ曲がってしまうのか、不思議なことですが、いや、恐ろしいことですが、自分はその契約に、律法に、神の御心に極めてよくお仕えしていると言いながら、神の独り子イエス・キリストを十字架につけて殺してしまうほどに、我々人間は、神にお従い出来ない罪人でした。しかし、この人間の罪が絶頂に達したキリストの十字架において、主なる神様は私たちと新しい契約を結んでくださいました。
キリストの出来事を通して、人間を義と断定する新しい契約、主イエス御自身が最後の晩餐の席で、「この杯は、あなたがたのために流される、わたしの血による新しい契約である。」と言って、打ち立ててくださった神と人間との新しい契約です。この新しい契約に生き、この新しい契約を人間に伝える務めにパウロと私たち教会は生きています。この務めは、モーセの「人を罪に定める務め」とは違い、「人を義とする務め」、しかも、11節では、モーセの仕えた「消え去るべきもの」に対して、「永続するもの」と呼ばれています。
なぜ、この務め、そしてこの務めが指し示す実体である「新しい契約」は、決して消え去らず、永続するのでしょうか?それは、人を義とするのは、人間の側の条件ではなく、恵みの神さまだからだと言うことができると思います。私たち自身のあり方には左右されないのです。風に揺れ動く葦であり、くすぶる灯心である私達の側の状態には左右されないからです。
そして神さま御自身が、それを契約と呼んで、御自分のことを縛り付けてくださるからです。このパウロの「永続するもの」という表現からは、エレミヤ書31:31で初めて語られた「新しい契約」をまた、32:40で、「永遠の契約」と言い換えてみせて、言葉の響きがここにリフレインしていると思います。
先週結婚式がありました。お二人と結婚準備会をしながら、こういうことを語り合いました。結婚というのは、30年先、40年先に、二人で一緒に居られてよかったと言うためにするものです。けれども、30年後、40年後の気持ちなんてわからないのに、一生の契約を結んでしまうのだから、覚悟のいることです。好きで結婚したんだから、嫌いになったら別れればいいでは、結婚する必要はない。それは少なくとも、教会が考える結婚式ではない。そこまで理解して、自分の体に消えない入れ墨を入れるような覚悟で、結婚式をして欲しい。もちろん、結婚は二人の同意と誠実の誓約によって成り立つものですから、その誠実の誓いが破られれば、終わってしまう可能性のあるものです。けれども、契約ですから、気持ち一つで自由にくっついたり別れたりできるものではありません。少なくとも教会はそう信じます。契約というのは、ある意味では、自分の自由を縛り、放棄することです。
神さまは、新しい契約を永遠の契約と呼ばれることにより、自分の自由を制限されたのです。しかも、多くの人が言うのは、この新しい契約は契約と言っても、神さまと人間が相互に同意をし、お互いへの誠実を誓って結ばれた相互契約ではなく、神さまからの一方的な契約、片務契約、片方だけが履行の義務を負う契約、だから、これは契約と言うよりも、約束だと言います。永遠の約束です。だから、パウロができることは、ある人を罪に、またある人を義に定めることではなく、義に定めるだけです。しかも、人は独りで何でもできるという浅い、うさん臭い、ポジティブシンキングを宣言するのではなく、神の恵みにより、我々はどんな貧しい者であっても、弱い者であっても、必ず生きていける、神が生かしてくださるという意味での、人の義を宣言するのです。
6節後半の「文字は殺しますが、霊は生かします」という有名な言葉は、旧約は捨てて、まだこのパウロの当時は、文字化されていなかった聖霊の語りである新約に生きるということではなくて、この私たち人間を生かそうとする神の息吹を忘れてしまえば、聖書はいつでも、人間を殺すことになるということだと思います。キリストの福音であっても、まかり間違えば、私たちを殺す文字になり得る読み方があると思います。それはもう一度、申しますが、御言葉を与えたままに、「さあ、これを実行せよ」と、人を御言葉の前に放り出すことであり、それは、言い換えれば、神さまの恵み、資格を与えられたのだから、今は、人は独りで何でもできると語ることだと思います。神の御前に大胆に確信を持って立つことができると語ったパウロは、決してそのような大胆さを語ったわけではありません。神がキリストにおいて打ち立ててくださった永遠の約束のゆえに、許されて、傍らにあるキリストに支えられて神の御前に立つ自分の確信を語ったのです。
このように神の御前に立たされた者は、どんなに努力しても、神の義にふさわしい条件を自分の側で整えることはできないことを悟りますが、しかし、なおいっそう、神にふさわしい者として、神の言葉に生きようと努力すると思います。ひりひりするような努力ではなく、遊びとしての努力、しかし、遊びであるからこそ、真剣に熱中して行う努力です。ただ、神さまを喜ばせたいからです。しかし、それは、誉められるための努力ではありません。愛する方の喜びに仕えたい。私たちのことを喜んでくださる神さまと一緒に喜びたい。義務でも、報酬を求めてでもなく、まして審判を恐れるからでもなく、ただ神の喜びに仕えること、そのために人を義とする伝道の業に仕えることをしたい。その神の喜びに突き動かされる私たちの姿は、大胆で、自由で、必ず、輝いて見えるのです。

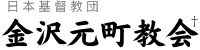
コメント