週報
説 教 題 「奉仕を誇らない」
聖書個所 コリントの信徒への手紙Ⅱ11章16節から33節まで
讃 美 歌 546(54年版)
私が所属している説教塾という学びの集団において、口を酸っぱくしてお互いに言い合うことであります。それは、聖書を読む心は旧約詩編119:130の御言葉に表されているということです。すなわち、「御言葉が開かれると光が射し出で/無知な者にも理解を与えます。」ということです。私たちは聖書の言葉を一所懸命に、自分への神様の言葉として聴く努力をしますが、本当にその言葉が、生ける神さまの言葉として響いてくるためには、聖書の言葉の方が私たちの所にやって来なければなりません。こっちが向こうに行くのではなくて、向こうからこっちに来て頂かなければなりません。説教の根本は、そのやってきた言葉を証しすること、だから、御言葉自身が打ちひらいてくるまで、待たなければならない。
言葉自身がやってくる。不思議なことです。けれでも、この不思議なことが起こるのです。聖書を読みながら、それを説く説教の言葉を聞きながら、突然、生ける神の言葉に直面させられるのです。「これは昔の話じゃない。私たちの物語だ。私たちに対する生ける神の語りかけだ。」説教者にも、信徒にも、求道者にも、黙想、解釈、適用という私たちの祈りの手仕事を越えて、御言葉自身がやってきます。私たちの目の前で立ち止まります。「これはあなたのことだ」と。「みことばうちひらくれば光をはなち、愚かなるものをさとからしむ」。
御言葉を打ちひらいてくださる方は、イエス・キリストの父なる神様であられます。だから、私たちが、御言葉の前から逃れられなくなるとき、私たちの前にやって来られたのは、生ける神様ご自身であります。より正確に言えば、神の言葉と呼ばれるイエスさまが、私たちの元に来てくださる。その霊におけるキリストの現臨、今ここに共にいます主に、私たちの目を開いてくださいます。これが聖書が証ししようとしている事柄、聖書が光を放ち露わになる事柄そのものです。
そのようにして、自分の目の前に開かれたキリストの現臨を、パウロはコリント教会のキリスト者たちに向かって、今日与えられました個所においても一所懸命に語っています。今、共にいますキリストの現臨という事柄そのものに、直面させるために語っています。その言葉は、なお、人間パウロの言葉でありながら、神の生ける言葉が開かれることを待っている祈りの言葉ではありません。彼自身には既に開かれ、生けるものとして響いている、今、共にますキリストの言葉です。彼の前に開かれ、彼を逃さず捕えてしまっているその生ける神の良き知らせを、生けるキリストを、事柄そのものを、何とかして伝えたい、何とかわかってもらいたい。しかし、その事柄そのものと直面させるために、パウロは真に人間らしい、あまりにも人間的過ぎるような言葉を語り始めます。
16節「もう一度言います。だれもわたしを愚か者と思わないでほしい。しかし、もしあなたがたがそう思うなら、わたしを愚か者と見なすがよい。そうすれば、わたしも少しは誇ることができる。」11:1の言葉と響き合っている続きの言葉です。「わたしの少しばかりの愚かさを我慢してくれたらよいが。いや、あなたがたは我慢してくれています。」
なぜ、こんなことをパウロが語るかと言えば、ずっと自慢話を続けているからです。自分の苦労話、自分の能力の高さ、自分の血筋の良さ、自分に注がれた神の恵み、自分の心の純粋さ、第11章から第12章の前半まで、言葉を尽くして語り続けているからです。自分が本物の神の使徒であることを認めてもらうために、自分のことを宣伝しているのです。あなたたちが私に代わって、自分たちの指導者として受け入れたあの人たちに比べて、私は少しも劣っていないと宣伝するのです。宣伝というものはそういうものだと思います。他と比べて自分の優れている部分を売り込むのです。宣伝というのは、結局のところ、たくさん並ぶ他の商品と比べて、自社の製品がいかに優れているか、あるいは、顧客にフィットするものであるかをアピールするのです。自分で自分を誇るのです。
こういう自己宣伝は、昔の日本では恥ずかしいことに数えられたかもしれません。自己PRは、厚かましいと人様から思われることです。しかし、現代はむしろ、受験でも、就職でも、積極的に自己PRすることが、求められているという面もあります。自分を上手く売り込んでいく能力は、仮に、その人の実態に合わなくても、自分たちのサービスや商品を宣伝してなんとしてでも売り込んでいきたい企業にとっては、どんなに厚かましくても、好ましい能力であると言えるのかもしれません。そうは言いましても、まだまだ、私たちも、完全に自己PRの価値観に染まりきっているわけではありません。受験や就職の際はいざ知らず、のべつ幕なしに自己推薦を続けることが、どんなに痛々しく恥ずかしいことであるかということは、やはり、よくわかります。その意味で、ここでパウロが自己推薦を仕方なしに一生懸命しながらも、それに言葉を重ねて、言い訳をする気持ちはよくわかるように思います。
本来ならば、自己推薦などすべきでないのです。だいぶ前の3:2には、「わたしたちの推薦状は、あなたがた自身です」と言ってましたし、少し先の12:11には、「わたしが、あなたがたから推薦してもらうべきだったのです」と言っています。本当ならば、パウロのことを他の人々に、「この方は、神の使徒です」と推薦する立場にあるコリント教会が、パウロを批判している。だから、本当はしたくないけれども、仕方なしに、あなたがたに私が使徒であることを、もう一度よく理解してもらわなければならない。だから、自己宣伝をするのだということです。
けれども、よく注意して聞く必要のあることがあります。パウロは、私たちにもよくわかるような気持ちをここで語っているようですが、私たちのよく共感できることとはおそらく微妙にずれています。微妙にずれて、自分を誇ることは、恥ずかしいことではなくて、愚かなことだと言っています。私たちは今日の22節以下でパウロが、次々と挙げているパウロの優れた点を、もしも、自分がパウロの立場にあり、教会の仲間に向かって語らなければならないとすれば、その自慢話は気持ちの良いことではなく、恥ずかしいことだと思います。
しかし、誤解でもなんでもなくて、事実、客観的にここでパウロが挙げているようなことどもが、自分の存在や手柄を語っているものであるならば、それを誰かの口で、表明してもらうことは、やぶさかでないと思います。きっと私たちはそこでも謙遜な態度を取ると思います。「それは言い過ぎです」と言うと思います。けれども、心の中では、どんなに嬉しいことかと思います。まして、自分が誤解されている、正当に評価されていないと思えば、自分のことを本当に分かってくれる人はいると、嬉しくなると思います。その言葉を聞きながら、確かに気恥ずかしい思いになると思いますが、その他者の評価を聞きながら、そんなことを褒めているその人のことを、愚か者だとは思わないでしょう。自分の良き理解者だと思うに違いないのです。
けれども、パウロが、ここで彼自身がしている自己宣伝を、恥ずかしいことと言わず、愚かなことだと言います。その時、それは本質的に、他者の口から語られるものであったところで、愚かであることには変わりがないのではないかと思います。22節以下で挙げられるパウロの自慢に値すると思えることどもは、本当は自慢に値するものなんかじゃない、まして、彼が神よりの本物の使徒であることの証拠には決してならないと考えているのです。なぜならば、こういった自慢話をパウロが始めるとき、最終的に行き着くのはいつでも、30節に語られるような言葉だからです。その言葉とは、「誇る必要があるならば、わたしの弱さにかかわる事柄を誇りましょう。」という言葉です。
自分は弱さ以外に誇るものはない、誇るならば自分の弱さだけを誇りたいと、いつもそこに行き着くパウロが、なぜ、ここでは、必死になって、自分を宣伝するようなことをするのか?コリント教会の人々がそこに価値を見出しているからです。主イエスと同じイスラエル人、ユダヤ人の血筋である。アブラハムの子孫として、正統な神の民の血筋である。パウロの後から来た伝道者たちは、自分たちが世界最初の教会エルサレム教会との繋がりを持つ由緒正しい伝道者であることを自分たちの推薦状としていたのだろうと考えられるとお話してきました。すなわち、自分たちが、ユダヤ人であることに誇りを持っていたのだということだと思います。そのことが、神よりの本物の使徒としての条件であると数えていたのだと思います。
コリント教会が惑わされたこの基準については、私たちはもう完全に乗り越えているように思います。少なくとも、私にとっては今のところ、別の事柄に当て嵌めてみて、たとえば、出身神学校や、出身教会を誇ったり、誰それ牧師から洗礼を受けたことを誇るということが同じことかな?という適用をしてみなければ、あまり意味のある言葉には聞こえてきません。言葉そのものを大切に理解すれば、これは、割礼や、食物規定のように、教会が既にそこから自由になっている律法主義的な残りかすのように思われます。その意味では、コリント教会というものは、まだまだ生まれたばかりの教会なのだと思わされます。
しかし、23節以下にパウロが語りだす自慢に関しては、私たちも、そうのんびりと構えていられなくなります。なぜならば、そこでパウロが語りだす自慢とは、キリストに仕える者としていかに自分が献身的な奉仕を重ねて来たかということだからです。パウロはキリスト者として、ただ、キリストにお仕えする者であるがゆえに、自分の身に負わなければならなくなった、今の私たちには想像もできないような苦労を重ねてきたのです。投獄、むち打ち、石打ち、難破の末の漂流、飢え渇き、不眠不休の労苦などなど、キリストにお従いするゆえに、経験しなければならなかった伝道の労苦、奉仕の労苦を、これでもかこれでもかと数えて行きます。自慢すべき価値あるものとして、コリント教会の人々が大事にしている使徒の資質を物語るエピソードとして、あれもこれも数え上げて行きます。そうすることによって、21節後半「だれかが何かのことであえて誇ろうとするなら、愚か者になったつもりで言いますが、わたしもあえて誇ろう」というのです。
しかし、パウロは、このキリストのための労苦を自慢するときにこそ、23節後半でこう言わなければなりませんでした。「気が変になったように言いますが」。こんなことを自慢として数えるのは、自分の手柄として数えるのは、「本当に本当におかしい」ということです。キリスト教会の中にあって血筋を誇ることは、おかしなことであることを私たちは、基本的に弁えていると思いますが、伝道の労苦を誇ること、献身的な奉仕を誇ることが、「気が変になったように」と言わなければ、決して自分の手柄として数えることができないことだと、本当に弁えているかと問われるならば、私は全く自信がありません。自慢できることだと思ってしまいます。褒められたいと思ってしまいます。世の人が認めてくれなくても、教会の仲間、信仰の仲間には認めてもらいたいと思ってしまいます。パウロには見えているものが、まだはっきりと見えていないのだなと思わされます。それらのもの一切が損失であり、塵あくたに数える他なくなるほどの、キリストのすばらしさをまだまだ味わう余地が大いにあるということです。
しかし、少なくとも、このような自分の目の曇りがわかってくると、16-21節の前半までのパウロの言葉が、そんな私たちに対する痛烈な皮肉の言葉であることもわかってまいります。これからパウロが語る自慢を本当は、愚かな自慢だとコリント教会自身が一笑に付さなければならなかったのです。パウロがこれからするような自慢を聞いて、コリントのキリスト者たちは、本当は我慢などしてはいけないのです。何で、君たちは、こんなことを有難がっているんだ。こんな自慢話を喜んでしまうのだ。何で、受け入れてしまうのだ。これらのものを有難がり、追い求めることによって、あなたがた自身が、奴隷にされてしまっているんだ、食い物にされてしまっているんだ、顔を殴りつけられてしまっているんだ。そのことがわからないのか。では、わたしも愚か者になろう。あなたがたの有難がっていることの戯画となろう、漫画となろう。ピエロとなろう。わたしの血筋を誇ろう。そして、福音を見失い、気が変になったようにならなければ、口が裂けても自慢として数えることができないことだが、キリストに結ばれた私の労苦を数え挙げて見せよう。
なんだか苦しくなってしまいます。こんなことを使徒に言わせなければならないコリント教会の信仰、それは決して私自身が無縁とは思えない自分の信仰です。それがどんなにこの伝道者を苦しめていることか。けれども、この苦しみは自分の誇りにも、手柄にもならないとこの伝道者は言います。なぜならば、29節です。「だれかが弱っているなら、わたしは弱らないでいられるでしょうか。だれかがつまずくなら、わたしが心を燃やさないでいられるでしょうか。」パウロの伝道の苦労、奉仕の骨折りとは、已むに已まれぬ思いに駆り立てられてやっていることだと言うのです。いやいややっていることではありません。それから善意からやっていることでもありません。やらずにはおれないのです。居ても立っても居られないのです。「誰かが弱っているなら、私は弱らないでいられるでしょうか。」
この言葉を聞きながら、私たちはどうしても主イエス・キリストのお姿をここに重ね合わさざるを得なくなるのではないかと思います。私たちがマタイによる福音書の連続講解説教においても、また、この第Ⅱコリント書を読むにあたっても、何度も何度も思い出してきたマタイによる福音書9:36が語る、「群衆が飼い主のいない羊のように弱りはて、打ちひしがれているのを見て、深く憐れまれた」主イエスのお姿です。この憐みは、はらわたのよじれるような憐みだと、私たちは知っています。捨て置くことができないのです。主イエスの語られる御言葉、なされる御業の一つ一つは、この弱っている者を捨て置くことのできない已むに已まれぬ憐みが、実を結んだものであります。
宮本久雄というカトリックの神父でもある哲学者が、パウロ書簡を読みながら、この主イエスのお姿を思い出して次のような趣旨のことを言いました。今、ここで主イエスは私たちとはらわたを一つとされる。私たちの痛みをご自分のはらわたの痛みとされる。そうやって主とはらわたを一つとして頂いた者たちが、今度は、この主によって、お互いがお互いのはらわたになってしまっていることを発見する。私の痛みをご自身のはらわたの痛みとして、私たちをはらわたを一つとしてくださる主イエス・キリストを媒介として、私たちもはらわたを一つとする。それがパウロの体を張った言葉を通して明らかにされるキリストの体なる教会だと言います。
パウロの人柄の問題ではありません。伝道者、牧会者としての思いや、資質の問題ではありません。「だれかが弱っているなら、わたしは弱らないでいられるでしょうか。だれかがつまずくなら、わたしが心を燃やさないでいられるでしょうか。」キリストの憐みのゆえにはらわたが一つだからです。愛してやっている。我慢してやっている。奉仕してやっている。牧会してやっているというのではありません。キリストの憐みのゆえに、はらわたが一つなのです。
そして私たちを已むに已まれず突き動かすそのはらわたの痛みは、兄弟姉妹の痛みでもありますが、やはり、今私たちと共にいます現臨のキリストご自身の痛みであります。今、私たちと共にいますキリストの憐みに突き動かされるのです。そうであるならば、私たちの伝道の労苦、奉仕の労苦は、どうあっても、誇れるようなものではないと思います。それはやはり、今、共にいますキリストご自身の労苦なのです。今、共にいますキリストご自身の燃えるような狂おしいほどの愛なのです。
そのキリストとはらわたを一つとして頂いているのは、パウロだけではありません。既に5:11以下で語りました。コリント教会も、そして私たちも、既にこのキリストとの一体の内に生かされている者です。もはや自分自身のためには生きられない、今私たちと共にいますキリストのために生きる他ありません。ただ弱っている者だけではありません。弱さの共感ということには留まりません。躓く者、罪の心になお生きてしまう者のためにも、燃え上がる神の愛に、心燃やされるのです。自分の愛ではありません。今、共にますキリストの憐みです。30節、私たちは弱いままです。弱さ以外に誇るものはありません。
しかし、主イエス・キリストの父である神さま、永遠にほめたたえられるべき神さまは、この弱い私たちを用い、具体的な本当に具体的な、伝道と奉仕の労苦を、私たちにも味あわせてくださるのです。それはこの身と生活を持って、キリストの燃えるような憐れみを、今、ここで味わわせて頂いていることなのです。
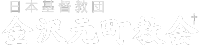
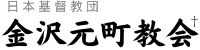
コメント