新しい年の最初の主の日に、神が私たちに語ってくださる御言葉と信じ、詩編第133篇を読みました。この聖書の言葉は、私たちの教会の年主題聖句であるのみならず、既に何年も、私たち金沢元町教会の見定めている教会の姿として、聞き続けている大切な聖書の言葉です。
「見よ、兄弟が共に座っている。/なんという恵み、なんという喜び」
ここで語られる情景は、私たちにもよくわかる喜びの情景です。兄弟と呼びあえる者たちが、共に座っている。おそらく、食卓を囲んでいる。そこで語らい、飲食をともにし、英気を養っている。
しかも、この際、ここで言われる兄弟とは、肉親の兄弟に限定されるものではありません。確かに、この詩篇は、元々は、肉親の兄弟が争わずにいることの、素晴らしさを語った詩ではないかと言われています。しかし、既に この詩編の第1節、見出しの部分に、「都に上る歌」という言葉が付されているように、この詩篇が聖書に加えられたかなり早い段階から、血の繋がりには限定されず、同じ信仰を持つ者同士の集まりの素晴らしさを語っているものと理解されるようになったと考えられます。たとえば、歴史的状況としては、バビロニア捕囚後の、ユダヤ人たちの姿が思い浮かべることができます。故郷を外国に占領された末、同信の仲間が散り散りにされてしまっている。その散らばった信仰の仲間が、年に一度、あるいは一生の内、数回だけ、エルサレム神殿の祭りに参加するために集ってくる。その道筋で、信仰を同じくする者と再会する。宿を共にし、同じ食卓を囲む。そういう喜びを語るものと理解することができます。もちろん、ユダヤの人々は、血筋と信仰を一つにする者たちです。信仰と血縁が分離しているわけではありません。肉の兄弟はそのまま信仰の兄弟でもありえたと思います。けれども、イスラエルの民と同じように、外国の軍隊によって征服され、占領国の各地に散り散りバラバラにされた民族が当時無数にいたにもかかわらず、ユダヤ人の先祖だけが、民族のアイデンティティーを保ち続けることができたのは、強固な血縁の結びつきによるものであったということはできません。むしろ、信仰において一つであったからだということができます。だから、この詩においても、単に肉の兄弟のことが言われているのではなくて、「都に上る歌」と、エルサレム神殿に詣でる時に歌われた歌とされ、信仰において結び付いた兄弟こそ、どんな困難の中にあっても、断ち切られない結びつきと自分が誰で何者であるかを語るアイデンティティーを与えるものであると、理解されていったことは、イスラエルの歴史の実体験に基づくことでもあったと思います。
この詩人は、そのような兄弟愛の姿を、「かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り/衣の襟に垂れるアロンのひげに滴り/ヘルモンにおく露のように/シオンの山々に滴り落ちる」と豊かな比喩で描写します。兄弟と呼べる者と共に過ごす時間は、さわやかな薫りに包まれるような心地よさ、高原で目覚めた朝の朝露に輝く緑を思わせる瑞々しい喜びがあるのだと言うのです。
ところが、ある人は言います。聖書を初めから読むと、「肉親の兄弟であれ、隣人であれ、同胞であれ、…「兄弟たちが一つになって住む」ということは、当たり前のことではないことがわか」ると。「この表現は、実際にはありえないことを表す比喩であることを理解して読む必要が」あると。この人は、私たちの新共同訳の翻訳では、「座る」と訳された言葉が、実は、「住む」という継続的な動作をも表す動詞であることを念頭に置いてこのように言います。年に一度、共に座ることができても、月に一度、顔を合わせることはできても、一緒に住むことは極めて難しいのです。
このように考えると、この詩篇の語る兄弟と呼び合える者の喜びは麗しいものでありながら、儚いものであることにも気付かされます。我々は、肉の兄弟であっても、実の肉親以上の、兄弟のように姉妹のように過ごす共との時間であっても、その関係が、変質から自由であるわけではないことも良く知っているからです。時の経過と共に、兄弟姉妹との、心地よい匂い油、高原の朝露のような良い薫りを放っていた瑞々しい関係の間に、色々なものが入ってきます。生きる場所が変わる。別の友人が入ってくる。恋人・配偶者という要素が加わって来る。社会的地位が変わる。経済状況が変わる。子供がいるのか?介護すべき親がいるのか?家族の形が変わる。そういうものの全てが、嫉妬や、違和感をもたらし良い匂いを変質させてしまうことがあります。
信仰の交わりにおいても、同じことが言えるかもしれない。もしも、私たちが、教会は神の家族だからと互いに近づきあい、肉親の兄弟姉妹のように、自分の我を出し合うならば、同じ神を信じていても、やがては破綻する関係になってしまうかもしれません。それが、人間です。人間の罪は深いのです。聖書が語る通り、同じ家庭で育った家族であろうと、同じ神を信じる者であろうと、カインとアベルのように、ヤコブとエサウのように、殺しあいかねないのが、私たち人間の本質であります。ならば、まして、違う家庭環境で育った者たちは、節度を持った距離というのをどうしても必要とするかもしれません。
しかし、なぜ、詩編の詩人は、そのような兄弟が共に座る美しさを、歌えるのでしょうか?失われていくものの美しさ、稀有な貴重な美しさだからこそ、歌う価値があると考えているのでしょうか?あるいは、 この世には存在しない継続的な友情、愛情への憧れを、この詩編第133篇を歌った詩人が、空想しているだけだということでしょうか?そうではないのです。この詩編は兄弟が共に座る美しさを現実のものとし、保証するものがあるゆえに、歌えるのです。この詩篇の三段落目。ここには、原語では、理由を表す接続詞が隠されています。
それを踏まえて、訳すならば、こうなります。
「(なぜならば、)シオンで、主は布告された/祝福と、とこしえの命を」。
このことは、ひとつ前の口語訳では、はっきりとわかります。口語訳はこう言います。「これは主がかしこに祝福を命じ、とこしえに命を与えられたからである。」
主が下さる祝福、主が下さるとこしえの命、これが、兄弟が共にいる美しさを作ると詩編第133篇は語り掛けます。この喜びが継続することを詩人が思い描けるのは、この詩人が賛美する兄弟と呼び合える者の集まりは、血筋、あるいは、住む場所、自分の趣味や、嗜好の一致によって生まれたものではなく、主なる神が下さる祝福、とこしえの命に基づく、神が下さった兄弟関係だからだと思います。
この御言葉によると、兄弟の一致を実現するのは、私たちが同じ信仰を持っているということですらありません。そうではなくて、私たちの信仰の先にいらっしゃる生ける神御自身が、祝福をくださるから、兄弟の一致は生まれるのです。それは、神の業だということです。「わたしはあなたがたが兄弟として共に生きることを望む。そのために、祝福を与える。永遠の命を与える。」という神の願いだけが、兄弟のかぐわしい一致を作るのです。
我々は、この詩人以上に知っています。私たちに祝福ととこしえの命を与えてくださった方がいることを。それは、イエス・キリストです。
まことにこの聖書個所と響きあうような不思議なことですが、主イエスは祝福ととこしえの命を私たちに与えるために、われわれの兄弟となってくださいました。この方との関係だけは、変質することがありません。なぜなら、この方は神の御分でありながらそれに固執することなく、私たちのために、私たちと同じ人となられた方だからです。他の誰も着いてきてくれない、共有してくれない友情、兄弟愛の終わる地点を突破し、我々のために、死んで下さるために人となられたのです。このことからすれば、詩編第133篇が歌う兄弟と座る喜びとは、主イエスが私たちの永遠の兄弟となっていてくださることにおいて本当の意味では実現していると言って構わないと私は思います。しかも、この方は、この方だけが私の真の友、真の兄弟になってくださったのではなくて、この方を通して、この方が命を懸けて、この方の友とされ、兄弟として頂いた者は、この方の父を自分の父として頂いたのであり、また、この家族にしていただいた私達同士が、この方を通して、真の兄弟となり、姉妹となるようにしてくださったのです。どんなに合い入れないものを抱えた者であっても、このキリストにあって兄弟とされています。キリストを兄と仰ぐゆえに、仰ぐ者たちはキリストの弟、妹として互いに兄弟です。最初のキリスト教会は、まさに、人種や、身分の差を乗り越えてできた集まりでした。そこには、ユダヤ人もいればギリシア人もいました。ファリサイ人もいれば徴税人もいました。男も女も同じところに座り、神の言葉を聞きました。奴隷もその主人も教会では同じ一つの食卓を囲みました。奴隷を働かせたままで、主人だけが先に教会の食卓に着くことは、禁じられたのです。これらのことは、それまではあり得ないことでした。
しかし、この稀有な一致は、今から私たちが作り出すものではありません。既に、教会の前提となっていることです。ガラテヤの信徒への手紙3:27以下にもこうあります。
「あなたがたは皆、信仰により、キリスト・イエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなたがたは皆、キリストを着ているからです。そこではもはや、ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません。あなたがたは皆、キリスト・イエスにおいて一つだからです。」
ここに今日、集められた仲間は、キリストの死と命が結びつけた者の集いです。キリストの死と復活によって、兄弟とされ、姉妹とされた者、あるいはその群れに加わるように、招かれている者達の集いです。決して壊れない関係がここにあります。
この兄弟関係、家族関係は、何も私たちが互いに秘密を打ち明けあわなければ成立しないものではありません。胸襟を開いて交わりの中に入っていかなければ、神の家族になれないなんてことはありません。その点、共に同じ時間を長く過ごせば過ごすほど、家族らしくなっていくという世の常識はここではそのままであることはありません。
かつて日本の代表的な説教者の一人と数えられた竹森満佐一牧師は、その点、徹底していました。自身の牧会していた吉祥寺教会の日曜日には、礼拝以外のプログラムを極力入れないという教会形成をいたしました。そこには一つの信仰的確信がありました。私たちが礼拝ごとに告白する使徒信条の中の、「聖徒の交わりを信ず」という文言。これは原文のラテン語では、聖徒と訳せると共に、「聖なる物の交わり」とも訳せる言葉です。竹森牧師はこの理解に基づき、教会は聖徒の交わりだから、クリスチャン同士親しくならなければいけないと人間的な親しさばかりを求めるようになる、これは誤解であると言うのです。
そして、この誤解のままに教会生活を続けるならば、「性質がちがったり、環境のちがう人間のあいだで、そういう交わりをつくり上げることは難しいからといって、失望するか、その中の何人かの人たちだけが、居心地のいい交わりをつくってしまう」ことになってしまうだろうと言います。しかし、聖徒の交わりとは、聖なる物の交わりという意味もある。それは、洗礼と聖餐の聖礼典を指す言葉で、「一番もとをただせば、これは、キリストとの交わりのこと」を言うのだと言います。聖徒の交わりとは、キリスト者同士の交わりであるには違いないけれども、それは、洗礼と聖餐、そして御言葉において御自身を与えることを選ばれたキリストに与るというところでこそ、一番よく見えるようになる交わりだと言います。それは、こう言いかえても良いと思います。ここには、どんな者がいても良い。教会の中で、気が合う者、気が合わない者同士が居続けたって少しもかまわない。その両者を結び付けるのは、人間的な親しさではなく、キリスト御自身なのだということです。しかも、その結びつきは、肉の兄弟を超える、まるで一人の人のような結びつきなのだということです。竹森牧師は、それを徹底すべく、礼拝後には何もプログラムを入れない、一言も話さずとも、聖徒の交わりは破れないということを実践する教会形成さえしたのです。
私どもは、そのような行き方はしないかもしれません。私たちは心だけではなく、体を持った存在ですから、お互いの具体的な生活の状況や祈りをシェアするのは、むしろ、一つの体として自然なことであると信じます。けれども、竹森牧師のあり方も忘れることはできません。ただキリストにこそ、私たちを結ぶ絆の基があるという基礎と中心を忘れれば、教会の交わりは、一時は、人間的に親しい良いものに見えても、必ず、崩れざるをえません。ただ、御言葉と、聖礼典において、現に、ここにいてくださるキリストが、私たちの心がどんなにバラバラに離れていくときも、決して分解しないように、教会を繋ぎとめてくださる御方です。だから、他のどんな交わりがなくとも、どんな要素が教会からなくなっても、説教と聖礼典に与ることは、教会が聖徒の交わりであるためになくてはならない教会の命です。
しかし、それだからこそ、一歩踏み込んで、隣に座る仲間の、安否を問う自由も与えられているのだと信じます。キリストがいて下さるから、どんな失敗をしても、やり直せる関係、それが教会の交わり、教会が神よりそれを告げるように託され、世の人々をその中に招く交わりだと信じます。キリストの赦しの中に、それだから、神との和解の中に、そして、この神の赦しと和解に支えられて、人間同士の和解の中に、人を招くのです。
私が、この聖書の言葉について、忘れることのできないのは、おそらくこの詩編第133篇の言葉が、キング牧師の、有名なI have a dream.の演説の背後にあった聖書の言葉だと考えられているということです。すなわち、この御言葉は、排他的な信仰者の閉鎖集団を作る言葉ではなく、今は具体的に敵味方に分かれているような人たちが兄弟として本当に共に座る食卓を思い描くビジョンを見せる神の言葉だということです。
私たちは、神の隠された目立たない、しかし、確かな「なぜならば」を信じます。キリストにおいて、「主がかしこに祝福を命じ、とこしえに命を与えられたから」、既に、兄弟とされた人間たちであることを信じます。その事実を先に示され、受け入れ、ただ恵みにより、既に、目に見える兄弟の一致、交わりを、この教会で、礼拝において、聖餐の食卓において、そして、それに基づいた日々の交わりにおいて、味合わせて頂いている私たちであることを喜び、また、今週も和解のために送り出されていくのです。
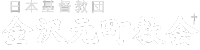

コメント