詩編第130篇
主イエス・キリストのご復活を時を定めて改めて思い起こす復活節の日々を過ごしています。このイースターは、私たちにとってクリスマス以上に大切な祝いだとも言えます。と言うのも、教会は、クリスマスを祝うことを知らない時期がありましたが、イースターを祝わないことなど、一度たりともなかったからです。そもそも私たち教会の集いは、イエス・キリストがお甦りになったということから決定的に始まりました。キリストのお甦りになられたことを思い出し、祝うためにこそ、毎日曜日、一つの場所に集まるようになった人びとこそが教会なのです。
その意味では、私たちは、年に一度、この季節だけ、主イエス・キリストのお甦りを祝っているのではなく、日曜日ごとに祝っている。教会とは、そもそも、キリストのお甦りを祝う場所だという言い方もできます。一体なぜ、イエス・キリストがお甦りになられたという知らせが、祝いとなり得るのか?なぜ、2000年間、毎週毎週祝わなければならないほどのことであるのか?
そのことを新鮮な思いで受け取るために、私は、教会のとても古い一つの慣習をご紹介したいと思います。それは、「復活祭の笑い」という慣習です。私たち日本人に福音が伝わった時には、この慣習はもう消えてしまったので、それは、耳新しいことであるかもしれません。けれども、たとえば、今でも東方教会やドイツのカトリック教会には残されている風習であるようです。「復活祭の笑い」、何をするかと言えば、イースターになると、皆、教会堂に集まってくる。そして、そこでみんなで大笑いするそうです。教会で大笑いするのです。礼拝中に、皆で「わっはっは」と大笑いする。なぜ、笑うのか、何を笑うのかと言うと、死を笑うのです。この世の中で私たち人間が一番確かなものだと思い知らされている死の力を笑うのです。キリストのお甦りのゆえです。キリストが甦られ、絶対だと思っていた死が絶対のものではないことが明らかになりました。しかも、このキリストを甦らされた父なる神は、キリストのゆえに、私たちの父でもあるのだと私たちには教えられています。だから、キリストのお甦りは、ただキリストお一人だけのものではなく、私たちの先駆けとしてのお甦りであったと教えられます。それゆえ、イースターには、その死の運命に縛られていた人間としての本当に深いところで、強張っていた心と体をほぐし、そして、大笑いするのです。
私が毎週のように引用しているカール・バルトという神学者はいつでも、私たちに聖書の言葉を新鮮な思いで新しく発見させてくれる人だと思いますが、信仰とはいったい何なのかと言うことについても、わかりやすいそして目の覚めるような言葉を語っています。バルトは、私たちの信仰とは、「自分にとって愉快なことを経験した子供が当然発する笑い」のようなものだと言いました。イースターの笑いと通じる笑いです。私は、この金沢元町教会に連なる者たちにとって、とても、素敵なことであると思いますが、教会の中で笑うということは、それほど、珍しいことではないと感じています。先日も集会室で、何人かの人たちで集会の後で集まってお茶をしていて、私もそこに入れてもらって、何気ない毎日の話やテレビの話をしながら、そこで、おかしくておかしくて、大笑いしました。 みんなで大笑いしながら話せる教会に遣わされたことをまた、心から感謝いたしました。教会にも、キリスト者にも笑いは似合うものだと思います。キリスト者は、自分の生まれながらの性質というのではなくて、神の下さる喜びが尽きることがないという理由で、愉快さと明るさを湛えるものであると思います。
けれども、これはキリスト者はいつも明るい顔をしていなくてはならないという律法ではありえません。これは、子どもの笑いであり、だから、本当の笑いであり、作り笑いとは正反対のものだからです。率直な笑い、自由な笑いです。私たち神の御前に生きる者たちは率直であって良いし、自由であって良いのです。それは、私が勝手に言っていることではなくて、聖書が言っていることです。典型的には、エフェソ3:12で、キリストに結ばれることによって与えられた私たちの在り方とは、「確信をもって、大胆に神に近づけることができ」ることだとあります。
この「大胆さ」とは、原語でパレーシアという言葉で、「率直」とも訳せるし、「自由」とも訳せる言葉です。キリスト者とは、神が作り出してくださる神の御前における大胆さ、率直さ、自由さに生きる者、それは、私たちを笑うようにする自由さであります。しかし、それはまた、同じように、御前に嘆くことを許してくださる自由でもあり得ることを聖書の言葉に即して確信することができます。それゆえ、今日共に聞きました御言葉、旧約詩編第130篇の祈りの言葉に耳を傾けたいのです。これは、私たちの祈りの手本の一つとして、神が与えてくださった自由で、大胆な、真に神の者にふさわしい祈りであると思うのです。
この祈りは、深い淵の底から、つまり、それは単純に深い苦しみの経験の中から、このように祈りだすのです。「わが主よ、私の声が聞こえますか?あなたに私の声は届かないのですか?」詩編の祈りはすべて私たちの祈りの模範として与えられているものです。歴史的にもそういう役割を果たしてきました。しかし、おそらくここにある祈り第130篇は、他の嘆きの詩篇のいくつかと同様に、私たちが自分の祈りの模範とするには、あまりに、意外な言葉で始まっていると思えるかもしれません。詩編第130篇は自分が嘆く声が、神様に聞こえていないと祈り始めます。だから、耳をそばだててよく聞いて下さいと祈るのです。言い換えれば、このような祈りを祈らなければならない者は、自分と神さまとの無限の隔たりを感じているのです。
この祈りは、ただ、机の上で、考えられた祈りではなく、実際に祈られてきた祈りであると言われています。一人の人の祈りであるかもしれないし、無数の人びとの祈りの言葉が、長い時を経て、このような形に結集したのかもしれませんが、いずれにせよ、これは実際に祈られた祈りです。この祈りを祈る人は、自分が暗闇の底に落ち込んでしまっていると感じている。その生涯は今、暗い暗い暗い穴の中にあります。しかも、この「深い淵」は、原語では複数形で書かれています。深い淵の下に、また、深い淵がある。だから、ある人は、これを「底なしの深みだ」と訳しました。それゆえ、その苦難の経験は現在進行形であり、まだまだ、落ち続けているという思い、神様との距離がぐんぐんと離れて行ってしまっていると感じながら叫んでいると言えます。
「主よ、この落ち行く私の声を聞き取って下さい。あなたに声が届くとは思えないこの場所で嘆き祈るわたしの声に耳を傾けて下さい。」そのような祈りであると言えます。私は深い淵の底にいて、神さまは天におられる。神さまとの無限の隔たりを感じているのです。だから、これは、もし、私たちが誰かある人の口から同じ言葉を聞けば、「そんなはずはない。神様は近くにおられるよ」と、まるでヨブの友人のように、言いたくなってしまうかもしれない嘆きの言葉です。
けれども、私は、なお、この嘆きの中には、何か輝くものがあるような気が致します。嘆いている。けれども、諦め切っていない。わたしたちはこの信仰者の嘆きを聞くとき、もしも、そこに絶望に支配しつくされている人を見てしまっているとしたら、少し、考えを改めなければならないかもしれません。すなわち、この嘆きの言葉に耳を澄ませるとき、それは、今もなお、落ち続けている底なしの絶望に支配されている徴ではなく、むしろ、絶望に支配されつくしてはいない者の姿を見るのです。何度も何度も、この嘆きの言葉を読む内に、私は深い淵の底から神に向かって祈る言葉の内に、そんな信仰者の姿が見えてくるような思いが致しました。
「深い淵の底から、主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取って下さい。嘆き祈るわたしの声に耳を傾けて下さい。」この祈りは知っているのです。神様は、本当は決して遠くにおられるべき方ではない。私の危機を見過ごしにされ続けるお方ではない。それは私に対する神様の最後の態度ではありえない。この嘆きの中にあって、すでに、神に期待し始めています。そのことは何よりもこの嘆きの言葉の内に、「主よ」と神様を呼ぶ、この祈り手のこの呼びかけに、表れていると思います。
この「主よ」という言葉は、アドナイという言葉から訳されました。アドナイ、「主よ」という呼びかけ。もしかしたら、わたしたちは、「主」というお名前は、イスラエルの神を、一般的客観的に、いわば、その名を発音する者とは、無関係に表現される名称だと、考えているかもしれません。しかし、「主」という神のお名前は、独立したお名前ではありません。それは呼ぶものとの関係を前提とした呼び名です。主は一人で主であることはありません。すなわち、神に向かって「主」と呼びかけるその人は、その呼びかけによって、既に、自分がその主の僕であることを前提としているのです。 すなわち、この祈り手によってアドナイと呼びかけられるお方は、深い淵から神様が私の言葉を聞いてくださらないと嘆く人の主人であられるのです。
それゆえ、「主よ」と神に呼びかける者は、たとえ、神様がどんなに遠く離れていると感じていても、なお、そのお方と自分の関係は完全に途切れてはいない、私と神様の間には、切っても切れぬ繋がりがあり続けるのだと告白しているのです。
私は、この祈りの言葉に、励まされます。神様から遠く隔たってしまっていると思う時、神様がそっぽを向いてしまっているように、深い深い深い絶望の淵の底にいる時も、その中で、神様に向かって「わが主よ、あなたの僕の声に耳をそばだてて下さい」と祈ることが許されている私たちであることに気付かされるからです。この祈りは、嘆きの祈りですが、不屈の祈りであるとも思うのです。しかも、さらにもう一歩、踏み込んで尋ねてみたいと思います。それは私たちにとって、とても大切な問いです。
なぜ、この祈り手は、こんな風に嘆くことが出来たのだろうか?どんどんと深みに落ちていきながら、なんで神様と自分の関係は、決して断ち切られていないと信じることが出来るのでしょうか?自分の義しさを確信しているからでしょうか?正しい自分が不当な苦しみに会っていると神様に対して訴えたということでしょうか?
そうではありませんでした。祈る人は、3、4節において、神様と自分の関係が、どこまで行っても断ち切られることのない理由は、自分の側には全くないと言っています。「主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら/主よ、誰が耐ええましょう。」と言うのです。この人は、自分の正しさを語りません。むしろ、神様の裁きを受けて当然の人間だと言っています。そうであるのに、私が神様との間に、「主人と僕」という強い結びつきの中に置かれ続けていることを確信し、その主人に声を聞いて下さいと訴えることができる理由は、主なる神さまが、この私の罪を赦し、僕と呼んで下さり続けるからに他ありません。
祈りは続けて言います。「しかし、赦しはあなたのもとにあり/人はあなたを畏れ敬うのです。」印象深いことは、神さまが、私の主人であられるということは、神さまが私の罪を赦してくださるという信頼に基づいて告白されているものだということです。神さまが私の主であるということは、何よりも赦しに関係しているのです。
おそらく、祈る者がこのように祈るとき、彼は自分一人の経験ではなく、彼の血となり骨となっている、彼の心と魂に深く刻み込まれた、罪のイスラエルと赦しの神の諸々の出来事が思い起こされているのだと思います。それは、神の民イスラエルの経験そのものでした。この信仰者は、まさに、旧約聖書に描かれた憐みによってのみ、聖なる者とされた選びの民の一人であるゆえに、神様と自分の関係が、自分の業にかかっているのではなく、ただただ憐みによって保たれている関係であるからこそ、神様が彼の主人であり続けることを疑うことはないのです。それゆえ彼は、その赦しの可能性に言及した時、爆発するように歌いださざるをえませんでした。
「わたしは主に望みをおき/わたしの魂は望みをおき/御言葉を待ち望みます。/私の魂は主を待ち望みます見張りが朝を待つにもまして/見張りが朝を待つにもまして」彼は、彼の魂に深く刻みつけられた、罪を犯し、赦され、罪を犯し、赦された神と彼の民の物語を、今、彼に起ころうとしている彼自身に開かれた物語として歌いだすのです。
私たちは思います。苦しみの中、深い淵の中、神の言葉を、神の助けを待つということは、身じろぎひとつせずに、静まることではないかと。深い淵の中にいる者に与えられる助けが、淵に沈みこんでいく者に依存せずに、ただ、全く受け身に主なる神、その御言葉を待つということは、沈黙してじっと待つことだと考えるかもしれない。確かに神様の助けを待つことは、別の詩篇では、そのような沈黙の中に待つことを語っている場合もあります。けれども、この祈り手にとって、主なる神を待ち望むことは、生き生きとした行為となっています。
ここで「待つ」と訳された言葉には、「緊張して待つ」という意味があると言います。そのことは、この詩の祈り手が、「朝を待つ見張り」のたとえを用いて、自分が主なる神の助けを待つことを証しています。私達は、この祈り手が置かれた、現実的な敵の襲来に備える極度の緊張状態を知っているわけではありません。だから、張り詰めて、魂の底から、全身全霊を傾けて、能動的に生き生きと見張りのように喜びの朝を待つということは、わかりません。けれども、待つことはいつでも、声も挙げずに、喜びの到来をじっと待つことばかりではないということを、今回は叶いませんでしたが、過去二回、子どもの出産に立ち会った経験から少し、わかるような気がいたします。 呻きながら、叫びながら待つ。子どもが無事に生まれてくることは、夜の次に朝がやってくるほどに、確かなことではありません。しかし、喜びの時を、呻き、叫びながら待ち望むということは、ここで嘆き祈る人の待ち方と似ているかもしれません。主を、その御言葉を待ち望む。はやる気持ちで待つ。緊張しながら待つ。呻きながら戦って待つ。深い淵も、夜も、苦しみも最後の場所ではないと確信しているからです。
この詩篇の表題に、「都に上る歌」とあります。なぜ、これが都に上る歌なのか?神殿に行き、礼拝に集う途上で歌われる歌なのか?そのことが、次の7,8節で明らかにされます。
「イスラエルよ、主を待ち望め。/慈しみは主のもとに/豊かな贖いも主のもとに。/主は、イスラエルを/全ての罪から贖ってくださる。」
赦しの神を思い起こし、だから、「わが主よ」と、大胆に、神様に呼びかけ、このお方に爆発的な望みをかけるこの人は、今度は、彼を力づけたような、新しい証言者としての一つの声になります。
「イスラエルよ、主を待ち望め。/慈しみは主のもとに/豊かな贖いも主のもとに。/主は、イスラエルを/すべての罪から贖ってくださる。」
神が赦しの方として、私の主人でいてくださることを私たちが悟るとき、深い淵で、主なる神の救いを確信して待ち望む者は、同じように深い淵の底にいる人々を力づける者へと変えられるのです。ここにこそ、私たち教会の姿があると思います。
この教会の案内看板に書かれた聖書の言葉があります。その看板に書かれた牧師の名はまだ堀江先生のままですから、やがて変えようという計画がなされています。どんな御言葉にするか考えてくださいと言われましたが、私は掲げる御言葉を変えたいとはあまり思いません。こちらに引っ越して、少し落ち着き、夜散歩に出た時、一週間くらい前だったと思いますが、初めてまじまじとその看板を見て、私は、感動してしまいました。それが、この教会に連なる者たちの宣言のように見えたからです。第2コリント1:4のお言葉です。「神は、あらゆる苦難に際してわたしたちを慰めてくださるので、わたしたちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。」
私たちが、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができると語る御言葉です。そのような御言葉を掲げています。外に向かって、ここでは、そういうことが起きるのだと語りかけているのです。誰か立ち止まってこの看板を真剣に読んでほしいと思いました。一人ではありません。「苦しんでいる人よ、私たちはあなたの苦難を慰めることができる」と言っている群れが、ここにはあるのです。たじろいでしまうほどの言葉ですが、それは、確かに教会の言葉です。私はこのような元町教会の言葉を、この教会を誇らしくさえ思うのです。もちろん、その誇らしさとは突き詰めれば、私たちの神を誇る誇りです。
なぜなら、私たちが、大胆にそう言えるのは、私たちがここで神に慰められたからです。その慰めとは、ただ、苦難のすべてが取り去られたということではありません。そうではなくて、今、神の恵みによって、笑う者にされていると同時に、嘆くことも許されているという事実です。私たちには、神の御前における自由、大胆さを与えられているということ、まさに、私たちは赦されて存在しているということを知る慰めなのです。言い換えるならば、罪赦されて生きることの慰めとは、私たちが笑う時も泣く時も、神さまに肯定されて生きているということを知るということです。単純に、私たちはそれぞれの人生を神様が肯定してくださる人生として生きることが許されているということです。私たちは笑うこと時ではない。嘆くことも、許されています。そしてその時、一人で嘆くのではありません。私たちの嘆きはむなしくはありません。神の胸を打ち叩くようにして嘆くことができます。そこで慰められ、その慰めを苦難の中にある人に伝えることができます。
私たちは憚ることなく詩編第130篇の祈りを自分の祈りとして祈ることができます。私たちの罪深さが、どんなに深くとも、私たちがどんな者であっても、私たちと神様の関係は決して絶たれません。そのことを、私たちは、詩編の祈り手よりも今ははっきりと確信できるとさえ言えます。十字架で死なれ、しかし、3日目にお甦りになられたイエス・キリストを知っているからです。
このお方は、深い淵の底にいる詩編第130篇の祈り手もまだ下ったことのない深み、すなわち、「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」という「私の主」が、私を見捨て、その関係も断ち切られたという他ない場所で、なお、神は私が嘆きを訴えることのできる「私の神」であられることを教えて下さいました。このお方こそ、深い淵の底において、私たちの主であり続け、また兄弟でいてくださるお方です。
だから、私たちは、嘆くことしかできないときは、嘆いて良いのです。それが、私たちがキリストのものであり、神の子どもであるということなのです。その嘆きには既に、独特の明るさが、見え始めていると思うのです。親の胸で安心して嘆いている子どもを私たちが見るときの明るさです。そこに、私たちの生きる確かさ、神を呼ぶことの確かさがあるのです。
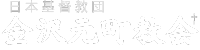
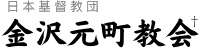
コメント