マタイによる福音書28:1-10
私たちの主イエス・キリストが十字架で死なれたのは、金曜日の午後3時ごろでした。そこから葬りまでは、とても慌ただしいものであったことが聖書を読むと分かります。私たちも身近な者が亡くなると、火葬に至るまで、本当に慌ただしい時を過ごすということを経験上知っていますが、それにしても主イエスの葬りは、私たちが葬儀にまつわる時の流れを知っている以上に慌ただしいものでした。
主イエスは金曜日の午後3時に十字架で叫ばれお亡くなりになると、その日の夕方には、墓に葬られたのです。ある本によると、当時は、人が死ぬと8時間以内には、もう埋葬したようです。暑い国なので、埋葬を急がなければならなかったということもあるそうです。しかし、それにしても主イエスが、死のおそらく2、3時間後に墓に葬られたということは、異例のことであったろうと思います。
その理由は、その日は、日が沈めば、何も仕事をしてはならない安息日が始まるからということができます。安息日が始まる前に、一切の仕事を終えなければなりません。午後3時過ぎ、そこから日が沈むまでの間に主のお体を十字架から降ろし、最低限の処置を施し、お体を墓に納め、重い大きな石の蓋をしなければならなかったのです。だから、慌ただしい葬りとなったと言うことができます。
ところが、当時の慣習として次のことも知られています。安息日であっても、やって良い仕事がいくつかあり、葬りの処置は、それに含まれたと言われます。しかし、主イエスの葬りの場合は、そうなりませんでした。おそらく、重大な犯罪人として死刑にされた主の葬りを進んで行おうという勇気が、実の兄弟の内にも、弟子たちの内にも湧いて来なかったからだと思います。ただ、弟子の一人であったアリマタヤのヨセフという金持ちの男性、この人は、ユダヤ人のお偉方にも顔のきく人であったようですが、彼が最低限の処置を施し、なるべく目立たぬように、人目を引かぬように安息日が始まる前に、主イエスを墓に葬ったのだと想像できます。それだけでも、勇気のいることであったと、マルコによる福音書では、伝えられています。だから、主の死から墓への葬りは当時の常識からしても、本当に慌ただしいものとなりました。
しかし、考えて見れば、死から葬りの時間だけが慌ただしかったのではありませんでした。最後の晩餐から、ゲツセマネの園での祈り、ユダの裏切り、逮捕、二つの裁判、鞭打ち、死刑、葬りに至るまで、すべては24時間以内に起きたことであり、本当に息つく間もない、あっという間の出来事であったと言えます。
ある人は、死というものは、いつでも、私たちを不意打ちするものだと言いました。いつでも思いがけない時に、死は訪れると言うのです。確かにそれは、主イエスの時だけではありません。たとえ、安息日に縛られていなくても、遺体を長く留めておける技術が進んでも、私たちが葬儀で経験する慌ただしさという事実は、いつでも死というものは、私たちを不意打ちするものであるということを物語っていると思います。弟子たちの内、誰一人として主イエスと十分なお別れをすることはできませんでした。
しかし、たとえ、一日の内に突然亡くなったのではなく、長く患った者であっても、これで、満足、これで十分にお別れが済んだということにはなかなかならないのではないかと思います。突然の死も、長患いの末の死も、死のその時は、いつでも、私たちにとって不意打ちのよう感じるのだと思います。それが、私たちの実感であると思います。だから、別れには、それを心に落とし込むための時間や、涙が別れの後にも、どうしても必要なのだと思います。
「安息日が終わって、週の初めの日の明け方に」と、今日共に聞きました聖書の物語は始まります。安息日が終わった翌日の明け方、私たちは、イースターの情景を、朝の光の内に起きた出来事と想像しますが、マタイの原文を読むと、別の理解も可能なところです。もう少し、原文に即した翻訳では、「安息日が過ぎ去り、週の第一日が明ける頃」となります。少しややこしいことを言うようですが、イスラエルの1日は、創世記第1章の「夕べがあり、朝があった」という表現からも分かるように、夕べ、日没から始まります。今のイスラム社会と同じです。 だから、原文が語るように、安息日が過ぎ去り、次の日が明ける頃とは、朝ではなく、夜であったと考えることもできます。つまり、二人の女性は、朝が来るのを待っていられなかった。安息日が終わると、夜の内に、主イエスの墓に向かった。そう読むこともできます。いてもたってもいられなかった、そういうニュアンスが伝わってきます。
夜も明けぬのに、二人の女性が主イエスの墓を見に行った。何のためでしょうか?私は、主イエスが本当に死んでしまったことを受け止め、自分の心を整理するためであったと思います。まともな葬りの準備も、まして葬儀を執り行うことができなかった主イエスとの別れをこのままではどうしてもできないと、その死に納得するために暗い内に墓にやってきたのではないでしょうか?そして、それ以外ではなかったと思います。そこでは、他の福音書のように、遺体に良い香りのする油をお塗ろうという意図も語られていません。墓を、死の現実を見に来たのです。
ある聖書学者は、マタイでは、遺体に良い香りのする油を塗ろうという計画が欠けているのは、マタイが、イスラエルの気候の厳しさをよく知っていたからだろうと考えます。主のお体は一日たって腐敗し始めていると考えられるのです。いまさら、匂い油を塗る段階にはないということをマタイは知っていたから、そうは書けなかったのだろうと言うのです。死は死であるということを、見つめている。だから、朝早く、あるいは夜の暗い内に、女性たちがやってきたのは、マタイがそう記すように何をするでもなく「墓を見るため」に他ならなかったと思うのです。そして、その望みこそ、死を前にして、私たちが望みうる全てであると思います。この短い第1節の言葉には、愛する者の死を前にしたそれからの私たちの生活があると思います。何年たっても、何十年たっても、私たちがやがて同じように死ぬまで、変ることのない、私たちよりも先に死んだ者との唯一つの在り得る関わり方です。それは、「墓を見に行く」ことです。その死を納得するための私たちのささやかな行為です。
けれども、第2節、そこで、この世界に教会が存在するようになった出来事が起きました。大きな地震、稲妻の輝きを持った雪のように白い衣を着た天使の出現です。しかし、これらの特別な描写は、先立つ一つの言葉に付随する二次的な描写にすぎないと私は思います。それらの奇跡的な描写が付き従う、突然起きた新しい出来事の中身、それは、この天使が、主の天使であり、「天から下って近寄」ったということだと思います。私たちの生きる世界である地上に、別の所から別のものがやってきたのです。「墓を見に行く」ことだけが慰めであるこの地に、天が下って近寄ってきたのです。主イエスの死が、墓の前で嘆く人々の姿で終わりにならないのは、人間の側に何か理由があるのではありません。たとえば、教会が生まれたのは、主イエスの死を無駄にすまいと心を奮い立たせた弟子たちの湧き上がる勇気によるのではありませんでした。その日、教会を生み出し、その出来事がそれ以来、語り継がれることになった理由は、私たち人間の知恵の深まりによるのではなく、その日、天が地に下り、近寄ってきたということに拠ります。
しかも、この私たち地にある者からではなく、上から下ってきた者によって起きた出来事は、私たち人間をそっちのけにして、無関係に起こったことではありませんでした。それは近寄ってきたのです。主の天使が天から下ってきたのは、二人の女性が、主イエスの葬られた墓を訪れた時なのです。天の力とは、私たちには理解できないような大きな力、そこに立ち会った者が、震え上がり、死人のようになってしまうような、大きな力です。けれども、それは、人間を歯牙にもかけない暴風のような力ではないのです。天使は婦人たちに語りかけます。「恐れることはない。十字架につけられたイエスを捜しているのだろうが、あの方は、ここにはおられない。」
死と墓の現実を乗り越える出来事との出会いは、ただ天より、主なる神の側より起こるということは、私たちが自分の生きているのが、地上であるということをリアルに噛みしめるならば当然であると言えます。この地には、どこを探しても、死を超える力はないのです。その死を超える力は、地上ではない天から、そして、強い死よりもさらに強い圧倒的な力でしょう。死の力は、確かに、地震、稲妻によって、表現されるような、出会う者を圧倒し、死人のようにしてしまう猛烈な力、主なる神の力によるのでなければ克服不能だと思います。しかし、私が、心動かされるのは、その死よりも強い主なる神の猛烈な力を体現している天使が、婦人たちの心を慮っているということです。
「十字架につけられたイエスを捜しているのだろう」という天使の言葉には、原文では「知っている」という言葉が用いられています。天は、よく知っているのです。私たちが愛する者の死を前にして、墓の前でどんな思いでいるのかよく知っているのです。圧倒的な力で死を打ち破る天のお方は、主イエスの告げられた復活を信じられず、墓を見に来た婦人たち、死の力に打ちのめされている、主よりも、死を信じるその心を知っていてくれるのです。しかも、その知識は責めるためではありませんでした。「恐れることはない」と語りかけるのです。「かねて言われていたとおり、復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。」死に打ち沈む者の悲しみを拭い去るために、死に打ち勝つ力を教えるために人間の心を知っているのです。 天使は、引き続いて婦人たちに使命を与えました。「急いで行って弟子たちにこう告げなさい。『あの方は死者の中から復活された。そして、あなたがたより先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。』」
8節には、この使命を受けた婦人たちの姿が描かれています。「婦人たちは、恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行った。」恐れながらも大いに喜んでいる、マタイはこの出来事に接して復活の証人とされた二人の婦人の心をそのように描写します。けれども、この記述は、マルコによる福音書と比べてみると、だいぶ様子が違うように思われます。
マルコによる福音書の平行箇所では、次のように記されていました。「婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして、だれにも何も言わなかった。恐ろしかったからである。」そこには、主イエスご復活の知らせと、証人としての使命を喜びの知らせと受け取り損ねているような婦人たちの姿が描かれています。しかも、多くの学者の意見によれば、マルコによる福音書は、この言葉で終わっていた可能性があると言われます。マルコ16:9以下が、カギカッコで括られているように、これは、古い有力な写本には載っていないのです。天使の知らせを聞いた婦人たちはただ恐れて逃げ去った。もしかしたら、マルコによる福音書はそれで終わっていた可能性があるのです。
けれども、マタイは、ただ、「恐れた」とだけ記さなかった。大いなる喜びが伴ったことを書いた。どちらがより正しかったというのでなくて、私は、こういう風に想像いたします。マタイもマルコも、婦人たちが、墓から走って行ったことを知らされていた。マルコはそれを大いなる神の出来事に打たれた者の恐れの姿として見た。それはその通りであろうと思います。もしかしたら、最初はそうであったかもしれない。けれども、マタイはそこに大いなる喜びが伴っていたことを付け足さざるを得なかった。なぜならば、マタイは、それに引き続いて起きた出来事を視野に収めているからです。
9節、「すると、イエスが行く手に立っていて、『おはよう』と言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。」
私はこういう風に思い巡らしてみたいのです。この最初の証人たちは天使の知らせを聞いてなお信じられなかったのかもしれない。ただただ、恐ろしいだけであったのかもしれない。墓から走り去ったのは、やはり、転げるようにして、その恐ろしい出来事の現場から立ち去りたかったからなのかもしれない。ところが、彼女たちが、墓から走り去ろうと向かった方向に、ご復活の主イエスが先回りして待っておられた。ただ、たまたま向かった先にいたわけではないのです。原文では、「会いに行く」「出迎える」という言葉が用いられています。走り去る彼女たちの元に主イエスが会いに来てくださった、彼女たちを出迎えてくださった。
新共同訳聖書には表れていない原語の話ばかりして恐縮ですが、さらに、主イエスが二人にかけた「おはよう」という第一声は、普通の挨拶の言葉でありながら、直訳すれば、「喜べ」という言葉です。主は恐れる者たちに「私の甦りは、あなたたちの喜びだ」と仰る。考えて見れば、主イエスのご復活は私たち人間にとって喜ばしいものであるかどうか、そのままではわからないものです。主イエスのご復活が人間にとっての喜びであるとは限らないということは、「一度生きたら十分。人生二度も生きたくない」なんていうおかしいような悲しいような強がりだとか、自分の人生は、大変な人生だったという感慨とは、まったく別のものです。主イエスのご復活が喜びとは限らないのは、我々がその方を十字架につけた罪人である人間という種族であるということに拠ります。
婦人たちも同様です。確かに彼女たちは、その場で最もふさわしく振る舞った人間であるかもしれません。けれども、その最上の人たちでさえ、「かねて言われていた」主のお言葉を信じることはありませんでした。 そして、私たちも彼女たち以上にましな人間だとは到底言えません。そのような不信仰な人間にとって、主のご復活は喜びであるとは限りません。その出来事は、私たちが神を信じない者、神に背くものであることを、最も赤裸々に告発する出来事であるとも言えます。
ところが、主イエスは、信仰のない者に「喜べ」と仰ってくださいました。「私の復活はあなたがたの喜びだ」と仰ってくださいました。主のご復活はただただ、私たちのためだったということです。それどころか、Ⅰコリント15:13の表現によれば、私たちの普通の考え方を全く逆転するように、パウロは、「死者の復活がなければ、キリストも復活しなかったはずです。」と述べ、私たちのためでなければ、そもそもキリストは復活されなかったとさえ述べることが許されているのです。 ここは近い内に、もう一回別の機会に説教をしなければならない豊かな箇所だと思いますが、パウロがこれほどまでに、キリストのご復活を私たちの利益と結び付けて述べるのには、たとえば、今日の聖書個所に語られているご復活のキリストの姿の記憶が教会に、強く残っていただろうからだと思います。
もう一度、シンプルに言い直します。私たちは心が頑なで主の復活を信じられないかもしれません。私たちは死の力と墓の現実に説得されているかもしれません。また、私たちは、この出来事が大きすぎて、自分には関係のないことだ、自分の希望とはなりえないと思っているかもしれません。その福音書の報告の異様さにどう受け止めてよいか、困惑するばかりであるかもしれません。
けれども、主は、私たちが、主のご復活が分かるまで、それどころか、それがまさに私たちの利益であり、喜びであることがわかるまで、徹底的に私たちを追いかけて来られると言うことです。さらに、正確に言えば、逃げる私たちの後ろから追いかけて来られるのですらなくて、走り去った先で、そこに先回りして出迎えてくださるのです。
このマタイのイースターの箇所から今日の説教準備をしていて、私は、最初不思議に思い、けれども、やがて、愉快で愉快で仕方がなくなったことがあります。不思議とは、最初に天使の告げた言葉と、走り去ろうとした婦人たちに出会ってくださった主イエスが告げた言葉が、ほとんど一緒であることの不思議です。
天使は言いました。「急いで行って弟子たちにこう告げなさい。『あの方は死者の中から復活された。そして、あなたがたより先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。』」
主イエスは仰いました。「行って、わたしの兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこでわたしに会うことになる。」
なぜ、同じことを二度告げなければならないのか?どうせ、婦人たちも弟子たちも故郷であるガリラヤに帰ることになるのに、なぜ、途中で、もう一度主イエス御自身が婦人たちの前に立って告げなければならなかったのか?私は他のどんな理由があるのでもなく、ただ主イエスの喜びの溢れるさまを見る思いがするのです。 一刻も早く、会いたいという主イエスの思いです。「ガリラヤに行けば会えるよ」と、本人が告げることは、真に不思議なことです。そこでは、もうご復活の主との出会いが起こってしまっているからです。けれども、それだけに、主の喜びの爆発を見るのです。ご復活の主との出会いを待ち望んでいるのは、私たち以上に、主御自身であることに気付かされるのです。ある説教者は言いました。「私たちを不意打ちするのは、死だけではない。甦りの主も不意打ちされる。甦りの主が、私たちを不意打ちするために、先回りしていてくださるのであり、それに捕らえられるということが、主イエスの恵みに生きるということだ」と。
その主が先回りしてくださっているガリラヤとは、私たちの生活の只中のことです。それは、弟子たちの故郷です。私たちの生きている場所のことです。私たちが向かうところ、そこに主イエスは先回りされます。そこで私たちを出迎えてくださいます。だから、それは、ここから出ていき、私たちが遣わされていく場所であり、同時に、今私たちが置かれているここでもあります。
今、この時、ここで聖餐を祝います。この食卓は、主がご用意くださった食卓、主が先回りしてご用意くださった食事です。この聖餐にあずかるとき、主は私たちと一つ体であり、共にいてくださることを私たちの心と体に刻んでくださいます。そして、そのように主と一つとされている私たちが、それぞれの場に遣わされることによって、私たちは、先回りしておられる主イエスが共にいてくださることを、全ての人に語るしるしとして用いられる者にさえならせて頂くのです。「わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。」という約束は、キリストのご復活が生み出した教会が存在しているという事実のゆえに、私たちにおいても、私たちと共に生きる全ての人にとっても、今ここにある事実なのです。
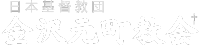
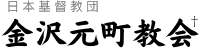
コメント