今日皆さんと共に聞きました御言葉を通して、私たちの主イエスは、「悲しむ人々は幸いである」と仰います。聖書の原語により忠実であることを目指した一つの翻訳では、この個所は「幸いだ、悲嘆にくれている者たち」とされています。
ここで主イエスが見つめておられる悲しむ人々と言うのは、悲嘆にくれている人なんだという発見は、私たちの想像力を刺激することだと思います。黙って悲しみに耐えているのではなく、その悲しみがもう抑えきれずに、声を挙げて嘆いている人に主イエスがまなざしを注いでおられる、そんなイメージが浮かびます。
たとえば、辞典を引いてみますと、ここで用いられている「悲しみ」という言葉(ペンセオー)は、人間の死が引き起こす悲しみの表現、お葬式において流される涙や、嘆きを表現する時に用いられる言葉だとあります。そこで辞典は、70人訳聖書と呼ばれるギリシア語訳の旧約聖書の創世記23:2をこの悲しみという言葉が用いられる代表例として挙げています。それは、信仰の父である老人アブラハムが、老齢になった妻サラを先に亡くした時の胸を打ちながら嘆いた悲しみを表す文章です。
「サラは、カナン地方のキルヤト・アルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは、サラのために胸を打ち、嘆き悲しんだ。」とあります。
噛み殺して押し留めることのできなかった悲しみです。嘆きとなって、胸を打ち叩きながら出た悲しみです。
私は、主イエスがそのような悲しみを見つめてくださっているというだけで、それだけで、とても有難いことだと感じます。主イエスは悲嘆にくれる人を目の前にしても、逃げられないのです。
正直に言いまして、このように嘆いている人を目の前にして、私たちはある種の居心地の悪さを感ぜずにはおれないところがあると思います。嘆いている人のそばに行くということは、それだけで、なかなか勇気のあることだと思います。めんどくさいことには関わりたくないという事ではなしに、本当に嘆きの中にある人のためには、どういう言葉をかければ良いのか?どんな顔をして隣にいれば良いのか?わからないからです。たとえば、旧約聖書ヨブ記において、財産と子と、健康を一度に失ったヨブの苦しみの前で、親友たちが、絶句してしまったという聖書の記述は、私たちにも本当によくわかることだと思います。
けれども、また、同じヨブ記において、そのヨブの苦しみを前に、絶句していた友人たちが、苦しみの中で自分の嘆きをヨブが口にし始めた時には、その言葉を聞くことがあまりにもつらくなり、そのヨブの嘆きを文字通りやめさせようと語った慰めの言葉もまた、私たちにとって、身に覚えのあることだと思います。ある人は、悲嘆にくれる者を目の前にするとき、「偽りの慰めや気休めを語るよりは、むしろ、黙っている方がよかった」、「場合によっては、相手を慰めようと滔々とまくしたてるよりも、黙って相手の気持ちを共有する方が、相手の心に言葉が届くということがあ」ると言います。ヨブ記16:2では、「そんなことを聞くのはもうたくさんだ。/あなたたちは皆、慰める振りをして苦しめる。」と苦しみの人ヨブは抗議の声を挙げていますが、私たちの慰めの言葉がしばしば、このような苦しみを悲嘆にくれている者に増し加えることが起こりうるのだという事を恐れないわけにはいきません。そこで、慰められようとしているのは、悲しむ者を目前にしたときの、私たち自身の戸惑う気持ちであるかもしれないと思うことすらあります。それゆえ、ヨブの友人たちの最初の反応のように、その悲しみと苦しみに圧倒されて、言葉を失って、ただ、隣に座っているだけという事の方が、どれだけ深い慰めをヨブに与えることができたろうか、そのお陰で、ヨブの凍り付いていた魂はほぐれ、語り始めることができたのではないかと思うのです。むしろ、彼らは黙っているべきではなかったかと思うのです。つまり、私たちは、嘆いている人のそばにいることが、とてもへたくそなのだと思います。どう言って良いかわからないし、下手な慰めの言葉で、ますます嘆きを深めさせるばかりということを恐れて、そこにただ留まるということもなかなかできないものです。
だから、私たちが悲しみに暮れる時、逃げずに、私たちの傍らにいることを覚悟してくれている人がいるという事は、それだけで、有難いことだと思うのです。悲しむ人々、悲嘆にくれている者にそのまなざしを向けられる主イエスというお方は、悲しむ者のそばにいることを覚悟してくださる主イエスのお姿であると思います。
しかも、私たちは、どんな悲しみの中にあっても、このお方の慰めだけは拒否する必要がないと思います。私の不幸は誰にも分かりっこない。私の悲しみは誰にも共有できない。私はこの悲しみの出来事においては、全く孤独なんだと、言う必要はありません。なぜならば、主イエスも深い苦しみをご存じだからです。悲しみを知る人こそ、悲しむ者を慰めることができるとすれば、主イエスが、その人だと言えます。教会が主イエス・キリストをまっすぐに預言した言葉と信じるイザヤ書53:3に描かれる神の苦難の僕は、前の口語訳聖書では、「彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で、病を知っていた」という印象深い言葉で語られていました。人間の悲嘆に目を留められる主イエス御自身が、「悲しみの人」であった。彼は高みから下々の悲しみを観察しているのではなく、御自身、悲しみを担っているのです。十字架の上で、「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」と叫ばれたお方は、私たちが神に見捨てられたと思わざるを得ないような出来事においても、私たちと一緒に歩いてくださいます。
しかも、私たちがこのお方の前では、この悲しみは私だけの悲しみ、世の中には、無数の悲しみがあるかもしれないけれど、私の悲しみは他の誰のとも違う、誰にも担ってもらうことのできない私だけの悲しみなんだと言うこともできません。なぜならば、聖書が、全頁を用いて語ろうとしているのは、主イエス・キリストが十字架とその後生涯において、担われた悲しみ、苦しみは、我々の病であり、我々の悲しみそのものであったと私たちは信じるからです。数百年前アメリカ大陸に奴隷として連れて来られた人たちは、独特の深い信仰の歌を歌いました。ルイ・アームストロングも歌ったことで有名な”Nobody knows”という曲は、「誰も私の苦しみや悲しみを知らないけれど、イエス様だけは知っていてくださる。栄光、神にあれ」と歌っています。誰も、どんな人も、私の悲しみと苦しみを共有できないけれど、イエス様だけは、それが、私の罪のせいで私の身に振りかかった悲しみであったとしても、それは、私の悲しみであり、痛みだと、肩代わりにしてくださいます。私は、この主イエスが共にいてくださるゆえに、私たちがどんな悲しみの中にあっても、不幸ではなく、主イエスのゆえに、一人で捨て置かれるのではない幸せを頂くのだと思います。
けれども、このお方が、その御言葉によって、悲しんでいる者の本当に直ぐ近くにいらっしゃることを明らかにしてくださるとき、その膝を突き合わせて語ってくださる御言葉は、常識外れの御言葉であるようにも感じられます。
「悲しむ人々は、幸いである」
ある説教者は、これは、主イエスにしかお語りになれない言葉だと言います。それは、人間には語ることが許されない不可能な言葉だと言います。牧師は、しばしば人の悲しみに出会わなければなりません。その悲しみの中に出向いていかなければなりません。しかし、そこで悲しみにうずくまる人に、「おめでとう、悲しんでいる人はさいわいです」と言ったらどうなってしまうのか?それは全く非常識なことです。悲しみを共感できないどころか、その悲しみを喜んでいるようにさえ見える言葉です。だから、これは私たち人間は決して語ることのできない言葉です。
けれども、この人間の語ることのできない言葉を主イエスが語ることがお出来になるというのは、いったいどういうことなのでしょうか?ある説教者は、この悲しむ人々の幸いを宣言するお方が、やがて、およみがえりになった方であることが、決定的に重要であると言います。主イエスというお方はただ私たちと同じように悲しまれ、また、私たちの悲しみを担ってくださったというだけではありません。そうではなくて、その悲しみを通り抜けられ、喜びへと至った方でした。私たちの悲しみをすべてご自分で引き取られただけでなくて、それを喜びへと変えてしまわれました。主はよみがえられたのです。だから、主イエスは、「私はあなたの悲しみを知っている」と慰め深い言葉を語られるにとどまらず、「悲しんでいるあなたは幸いだ」とまで仰ることができるのです。
私がここで思い起こすのは、まだ私が信徒だった頃、とても可愛がってくださった教会の老婦人が仰った言葉です。彼女には、身内に牧師がいました。夫を失って泣いていた彼女に対して、その身内の牧師と、親戚のキリスト者たちが言った言葉が忘れられないと言いました。「あなたの夫は天国に凱旋したんだ。何を泣くことがあるのか?」使徒パウロは、ほとんど彼の遺言のような手紙において、「わたしにとって、生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。」(フィリピ1:21)と言いました。また、同じ手紙で、「この世を去って、キリストと共にいたい」という熱望を語りました。死の先にキリストが両手を広げて私たちを待っておられるのならば、それは、確かに悲しむべき言葉ではなく、幸せなことだと言えます。
私は最近、私たち改革長老教会にとって、宝の書物の一つであると言えるハイデルベルク信仰問答を読んでいて、心が吸い寄せられるような死の理解が語られている一つの文章を見つけました。それは、問42とその答えです。問答はこのように問います。「キリストがわたしたちのために死んでくださったのなら、どうしてわたしたちも死ななければならないのですか。」、答「わたしたちの死は、自分の罪に対する償いなのではなく、むしろ罪との死別であり、永遠の命への入り口なのです。」キリストのゆえに、私たちの死は、わたしたちが滅びるという事を意味はしていない。私たちが死ぬとき、そこで死ぬのは、私たちの罪であるというのです。わたしたちの肉体が死ぬとき、それは、私たちが永遠に罪と別れることであり、私たちは、そこで永遠の命に入り口に立っていると言うのです。とても、面白い言葉だと思いました。死において死ぬのは、私たちではなく、私たちの罪だと言うのです。罪と完全にお別れした自分というのは、どういう自分なのだろうか?やはり、聖書が語るようにおよもがえりのキリストとそっくりになった自分なのだろうか?そう思うと、自分の死を想像することも、少し、楽しくなってくるような気がいたします。だから、キリストを知るものにとって、死ぬことは、不利益ではありません。これも利益の一つ、恵みの一つとして数えることが許されているということだと思います。
悲嘆にくれる者が幸いであるのは、その悲しみそのものに、価値があるからではないと思います。シェークスピアのマクベスの冒頭に登場する三人の魔女が「奇麗は汚い、汚いは奇麗」と価値を転倒させたのと同じ仕方で、神が喜びを不幸と呼び、悲しみを幸福だと呼ぶから、悲しむ者は幸いなのではないと思います。そうではなくて、悲しむ者が幸いであるのは、その悲しみをもたらした出来事が、私たちにとって、最後の出来事ではないからです。
私がたびたび引用いたします、神学者カール・バルトという人は、その死の前夜に親友トゥルナイゼンと東西の冷戦が危機的な状況にあることを電話でため息交じりに話し、しかし、こう言って電話を置いたと伝えられています。「そうだ。世界は暗澹としているね。ただし、意気消沈だけはしないでおこうよ。絶対に。なぜなら、支配していたもう方がおられるから。モスクワやワシントン、あるいは北京においてだけではない。支配したもう方がおられる、しかも、全世界においてだよ。しかし、全く上から、天上から支配したもうのだ。神が支配の座についておられる。だから、私は恐れない。最も暗い瞬間にも信頼を持ち続けようではないか。希望を捨てないようにしようよ。すべての人にたいする、全世界に対する希望を。神は私たちを見捨てたまいはしない。私たちのうちのただの一人も。私たちお互いみなを見捨てたまいはしない。支配していたもう方がおられるのだから。」どんな暗い出来事も、悲しみの出来事も、私たちの最後の出来事とはなりません。それが、キリストの御復活が告げるメッセージです。
けれども、若い私に、「あなたの夫は天国に凱旋したんだ。何を泣くことがあるのか?」と語られた思い出を話してくださった老婦人は、実は、この言葉をつらい言葉として記憶していました。私はそのことも忘れることはできません。そしてまた、その悲しみの涙が、夫が天国に凱旋したことを信じ切ることのできない、だから、御復活の主を信じ切ることのできない不信仰の涙であると言ってしまうこともできないと思っています。
私たちの真の主人は、死ではなく、イエス・キリストを私たちのために、死者の中から御復活させてくださった慈しみ深い父なる神様であります。神は私たちの父であられます。神さまが私たちにご自身を父としてご紹介してくださったということは、それは、私たちが胸を叩いて泣いて良い相手として私たちに身を向けてくださっているということだと思います。
しばしば私たちが経験することは、本当にどうしようもないことが起こった時には、やがて、涙は乾く他ないということです。どんなに悲しんでも取り返しのつかないことが起きれば、その涙は乾かざるを得ないのです。心が凍りついてしまうのです。東西ドイツ時代に、少年少女の宗教教育に当たっていた一人の宗教学者でもあるインゴ・バルダーマンという教師は、聖書の詩編を通して、子どもたちの凍り付いた心が、緩み、言葉を得ていく姿を証ししました。ベルリンの壁を越えて、西ドイツに逃げてきたとき、ようやく逃げてくることができたことだけを喜ぶことしか許されない雰囲気がありました。けれども、彼のクラスにいた幼い少女は、詩編の言葉を口にすることにより、自分の凍り付いた心に言葉が与えられていきました。「私たちは、四週間前にドイツ民主共和国を出てきました。だけど、私は私の猫をあちらに置いてこなければならなかったんです!」
バルダーマンは、詩編の存在と、山上の説教を見つめながら、私たちの神が、私たちに嘆くことを許してくださる神だと言います。
「悲しむ人々は、幸いである」と仰る神は、私たちに悲しむ許可を与えてくださる神です。もちろん、この悲しみは最後の出来事ではありません。けれども、神がこれを最後の出来事とは絶対にさせない御復活の御方であるからこそ、私たちは、嘆き悲しむことができるのだと思います。
私たちに悲しみをもたらした出来事が、どんなに取り返しのつかないものに見えても、御復活のキリストのゆえに、死を打ち破る神のゆえに、最後のものではないから、心を凍らせて、ずっと耐えなければならないものではありえません。神の胸を打ち叩くようにして、嘆くことができます。
迷子の子どもを見ていると、泣かない子がいます。強い子だなと思っていると、親が見つかると、途端に泣き出したりします。そんな時、私たちは思います。どんなに我慢していたんだろうか。「悲しみ人々は、幸いである。その人たちは慰められる。」父なる神に捨て置かれず、父に起き上がらせていただいた御復活の主が語ってくださいます。その御復活は私たちの為です。この言葉は、私たちのための言葉です。安心して泣くこともまた、許されているのです。
慰めとは、ギリシア語で、「傍らに呼ぶ」という意味があります。私たちは、このお方の傍らに呼ばれてそこにいるのです。そして、実に、主イエスがお送りくださる聖霊を指してご紹介した別の助け主、慰め主という表現は、この慰めという言葉の名詞形が用いられています。私たちの傍らにいてくださる、それどころか、私たちの内に宿ってくださる霊なる神です。そこでまた、私はこの私たちと共にいてくださる、私たちを住まいとしてくださる最も身近な神でいらっしゃる聖霊のお働きについて、忘れがたい使徒パウロの一つの言葉を思い起こします。
「同様に、”霊”も弱いわたしたちを助けてくださいます。わたしたちはどう祈るべきかを知りませんが、”霊”自らが、言葉に表せないうめきをもってとりなしてくださるからです。」ロマ8:26
たとえ、私たちの心が悲しみに凍りついても、私たちの内にいらっしゃる聖霊が、うめいていてくださいます。私たちよりも先に、私たちの魂の叫びに気付いていてくださいます。終わりの日に、私たちの目の涙をことごとく拭い取ってくださるという約束をくださる神は、この地上にあっては、私たちの涙を皮袋に貯めて数え挙げてくださる方であり、この聖霊において、悲しみで凍りついた私たちの張りつめた心に、うめきの風穴を開け、ため息をつかせてくださる御方であります。この神のゆえに、私たちは石の心ではなく、肉の柔らかな心で生きることが許されています。
その方の声に、私たちも声を合わせることが許されています。「悲しむ人々は、幸いである、その人たちは慰められる。」私たちは、この主イエスの御言葉を聴き、気づき始めています。既に、その慰めは今ここで、私たちの生きるこのところで始まっているのだと。
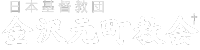
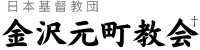
コメント